- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
遺産相続コラム
-
- 遺産を受け取る方
- 遺産相続
- 期限
- 土地
更新日:2025年07月02日 公開日:2022年04月19日
被相続人の遺産に土地や建物といった不動産が含まれている場合には、相続登記の手続きをすることが大切です。令和4年時点では、相続登記は義務ではありませんが、法律が改正され、令和6年からは相続登記が義務化されます。以降は、法定の期限内に相続登記をしなければ罰則が適用されますので注意が必要です。
相続登記をすることなく放置をすると罰則以外にもさまざまなデメリットが生じますので、相続が発生した場合には、早めに手続きを行いましょう。
今回は、土地の遺産相続に関して、相続登記の期限や放置した場合のデメリットなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 生前贈与
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求
更新日:2025年07月02日 公開日:2022年04月05日
相続税対策として、生前贈与が活用されることがあります。ただ、十分な生前贈与を受けた相続人であっても、相続開始後に、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うというケースはゼロではありません。
そもそも、遺留分とはどのようなものか、遺留分侵害額請求をされた場合にどのように対応するべきなのかわからない、という方もいるでしょう。
本コラムでは、遺留分の基本的な内容を解説するとともに、生前贈与がされた場合でも遺留分は発生するのか、また、遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 相続税対策
- 相続時精算課税制度
- メリット
- 注意点
- 手続き
更新日:2025年04月16日 公開日:2022年03月22日
生前贈与による相続対策を行う場合、贈与税や相続税の課税を検討することが必要です。
贈与税と相続税の課税を考える際、生前贈与への課税方式を「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかから選択することになります。まとまった金額の贈与を行う場合などには、相続時精算課税制度を利用する方が有利になりやすいので、税理士に相談してシミュレーションをしてみましょう。
この記事では、相続時精算課税制度のメリット、注意点および必要な手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 海外
- 預金
- 相続
更新日:2025年04月18日 公開日:2022年03月03日
近年では、海外赴任や海外移住する方なども増え、国外銀行に預金口座を開設している方が珍しくなくなっています。
そのため、遺産相続においては、ご家族が海外預金を残したまま亡くなられたために、相続手続きをどのように進めれば良いのだろうかと悩まれる方もいるでしょう。
本コラムでは、海外預金を相続するために知っておくべき知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 寄与分
- 上限
- 遺留分
- 遺贈
更新日:2023年09月21日 公開日:2022年02月22日
亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺言
- 経営者
- 遺言
- 会社
- 事業承継
更新日:2025年07月02日 公開日:2022年02月15日
会社経営者にとって、後継者への事業承継が視野に入ってくると、気になるのは「後継者や家族にどうすれば円満に財産を引き継げるか」ということでしょう。
事業承継が絡む遺産相続は、家族だけの問題ではなく、会社の取引先や従業員にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重に準備を進める必要があります。
特に会社経営者がトラブルのない遺産相続を実現するには、遺言書を作成しておくことが重要です。
本コラムでは、会社経営者が遺言書を作成すべき理由や、作成時のポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 利益相反
- 相続
- 問題
- 注意点
更新日:2025年08月25日 公開日:2022年02月02日
遺産相続の手続きを進める際は、「利益相反」に気を付けましょう。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。
利益相反行為を適切に対処しなければ、遺産分割協議や相続登記などもすべて白紙となり、最初からやり直さなければならない可能性があるため、注意が必要です。
本コラムでは、遺産相続で利益相反が問題となるケースや対処法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 不動産
- 相続
- トラブル
- 登記
- 税金
- 注意点
更新日:2025年07月07日 公開日:2022年01月25日
相続の当事者となると、他の相続人との交渉や役所での手続きなど、慣れない問題に対処していかなければなりません。特に遺産の中に不動産がある場合は、平等に分割することが困難で、遺産分割協議が難航する原因となりがちです。
そこで、不動産の相続に焦点を当てて「相続人の間でトラブルとなりやすい点と対処法」「相続開始から遺産分割、相続登記の手続き」「土地、一戸建て、マンションなど不動産の種類ごとの注意点」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 相続資格
- 重複
- 遺産資格
- 相続の進め方
更新日:2025年04月16日 公開日:2022年01月18日
民法の法定相続人を決定するルールに従うと、法定相続人になり得るのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
これらの相続資格について、ご家庭によっては、1人の相続人が重複して持ち合わせているケースが存在します。
相続資格が重複した場合、相続分の決定方法については、民法に明確な定めはありませんが、若干複雑なルールが適用されます。遺産分割協議においては、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかが非常に重要ですので、相続資格の重複に関するルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、相続資格が重複した場合における相続分の決定ルールなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割協議
- 相続債務
- 借金
- 分割
- 注意点
更新日:2025年07月07日 公開日:2022年01月11日
相続が発生し、相続財産を調べていたところ、多額の借金があったというケースは決して珍しいことではありません。
被相続人に借金がある場合は、遺産分割においてどのように分けることになるのでしょうか。また、相続人が借金を負担せずに済む方法はあるのでしょうか。
遺産分割における相続債務の取り扱われ方や、相続債務がある場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割協議
- 生前贈与
- 特別受益
- 違い
- 遺産分割
更新日:2025年07月02日 公開日:2021年12月21日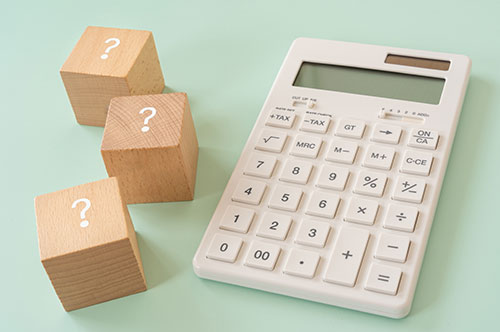
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 生命保険
- 死亡保険金
- 税金
- 相続
更新日:2025年07月02日 公開日:2021年12月14日
生命保険とは、病気やケガなど、保険契約に基づいた一定の保険事故が発生した場合に保険金が支払われる仕組みの契約のことです。
保険契約に従って受取人が保険金を受領するため、親族などが死亡して遺産相続が発生したという事実により、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人が承継する通常の相続とは異なる性質にあります。
生命保険(死亡保険)の被保険者が亡くなった場合、受取人が受け取った死亡保険金にかかる税金はどのようなものなのか、疑問に思う方は少なくありません。
また、特定の相続人のみが多額の死亡保険金を受け取っていた場合、平等に財産を分配する手だてはあるのだろうかと気になる方もいるでしょう。
本コラムでは、死亡保険金の相続税法上の扱いや税金・節税効果、遺産相続における扱いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- 相続人不存在
- 生涯独身
- 相続人なし
更新日:2023年09月08日 公開日:2021年12月07日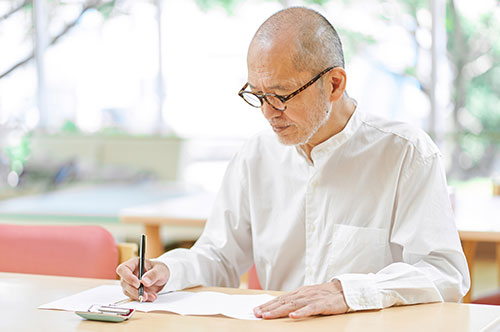
最近では生涯独身の方も決して珍しくありません。そのような独身の方が亡くなると相続人不存在(相続人がいない)という状態が発生する可能性があります。
そのような場合、遺産相続はどういう取り扱いがなされるのでしょうか。今回は相続人がいない場合の相続手続きの進め方について解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 代償分割
- 遺産分割
- 方法
- 不動産
更新日:2025年04月16日 公開日:2021年11月30日
相続が発生した場合、相続財産が現預金などの分割が容易なものだけであれば簡単ですが、不動産など分割が容易でないものの場合、相続人間で争いになる場合があります。
たとえば、兄弟のひとりは「土地を売却して現金を分配すべきだ」と主張し、他の兄弟は「土地はそのまま残しておきたい!」など意見が分かれる場合があります。そのような時に、活用したいのが「代償分割」です。
そこで今回は、相続の基本を確認しながら、代償分割の方法、配偶者居住権などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 祭祀財産
- 墓地
- 墓石
- 仏壇
更新日:2025年04月16日 公開日:2021年11月16日
被相続人が生前所有していた仏具などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として、通常の相続とは別枠で承継されます。
祭祀財産の承継ルールは、通常の相続とは大きく異なるため、法律上・税務上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。
この記事では、祭祀財産の承継者の決め方・相続税対策・トラブル防止のための注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- 遺留分
- 対策
- 生前
更新日:2023年09月20日 公開日:2021年11月09日
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- その他
- 墓
- 相続
- 手続き
更新日:2023年09月08日 公開日:2021年11月02日
親が亡くなったらお墓を相続しなければならないのでしょうか。お墓の維持管理が大変で相続したくない場合、放棄はできるのでしょうか。
お墓の相続は一般の財産相続とは異なる方法で進める必要があります。
今回はお墓の相続問題でよくあるお悩みや「祭祀(さいし)承継者」となったときのお墓の管理方法、かかる費用、相続に必要な手続きなどについて、弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 代襲相続
- 範囲
- 相続割合
更新日:2025年07月02日 公開日:2021年10月19日
相続人が死亡するなど、一定の理由により相続権を失った場合は、その子どもが亡くなった相続人に代わって遺産を相続するケースがあります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼び、代襲相続により相続することになった方を代襲相続人といいます。また、代襲相続とは、民法で詳細に規定されている遺産相続の制度です。代襲相続は相続割合や法定相続分の計算が変わることもあり、相続争いに発展するケースもあるため、注意しましょう。
本コラムでは、具体的に代襲相続とはどういった制度なのか、代襲相続人となれる範囲や要件、相続割合などについて、代襲相続による注意点を含めて、べリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
代襲相続は複雑なために理解が難しい点もありますが、基本的なポイントをおさえることから理解を深めていきましょう。 -
- 遺産を受け取る方
- 特別受益
- 持ち戻し
更新日:2023年09月08日 公開日:2021年10月18日
遺言がない場合には、相続人が法定相続分にしたがって遺産を相続するのが原則です。しかし、たとえば、被相続人が生前、長女と次女には結婚資金として600万円ずつを渡していたような場合、結婚していない長男は不公平と思うかもしれません。 このようなことを考慮して、民法では「特別受益」という制度を設けています。特別受益とは何か、特別受益として認められるものはどのようなもので、特別受益を得ていない相続人はどのような主張をすることが許されるのか見ていきましょう。 今回は、意外に知られていない「特別受益の対象」や「特別受益の持戻し」について解説をしていきたいと思います。
-
- 遺言
- 遺言書
- 偽造
- トラブル回避
- 対処法
更新日:2025年07月02日 公開日:2021年10月12日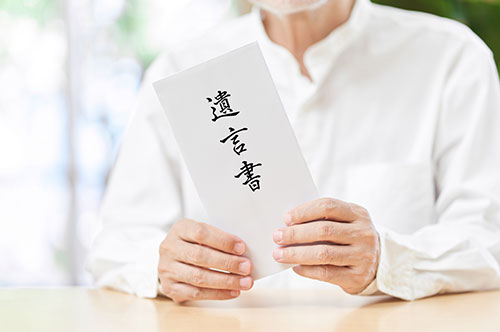
自筆証書遺言は、偽造や変造のおそれがある点が大きなデメリットといえます。
万が一、誰かしらに遺言書が偽造された場合、その遺言書に基づいて遺産分割がなされてしまうと不公平なものになってしまうおそれがあるでしょう。
その際は、適切な手続きを踏んで遺言の無効を争うことになります。
本コラムでは、遺言書の偽造が疑われるときの対処法や刑事罰、損害賠償請求などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム















