- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 相続財産清算人(相続財産管理人)とは? 役割や流れ、費用を解説
遺産相続コラム
相続財産清算人(相続財産管理人)とは? 役割や流れ、費用を解説
- 遺産を受け取る方
- 相続財産清算人
- 相続財産管理人
- 相続人がいない

亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
申し立てにあたっては、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任方法や必要になる費用などについて、事前に知っておくべきポイントがあります。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
ご注意ください
「相続財産管理人」は民法改正(2023年4月1日)により「相続財産清算人」へ名称変更となりました。
1、相続財産清算人(相続財産管理人)とは
-
(1)相続財産清算人(相続財産管理人)の役割
相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人がいない相続財産(遺産)を、最終的に国庫へ帰属させる役割を担う人のことです。
相続人がいない相続財産の国庫への帰属は、債権者や受遺者(遺贈を受け取る人)への弁済を経た後に行われます(民法第959条)。しかし、相続財産を管理する人がいない状態では、国庫へ帰属させることはできません。
そこで、家庭裁判所が相続財産清算人(相続財産管理人)を選任し、相続財産を国庫へ帰属させるまでの必要な職務を行わせることになっているのです。相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続財産法人(相続人がいることが明らかでない場合に相続財産が法人化されること)の法定代理人としての立場で、以下の職務を行う権限を有します。- 相続債権者および受遺者に対する弁済(民法第957条)
- 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法第958条の2)
- 残余財産の国庫への帰属(民法第959条)
なお、後に判明した相続人が相続の承認をした場合、相続財産清算人(相続財産管理人)の代理権は消滅します(民法第956条第1項)。
-
(2)相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を請求するための要件
家庭裁判所に相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を請求するためには、要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下の3つの要件を満たすことが必要です。① 利害関係人であること
債権者がいる・受遺者に対して遺贈を履行する必要があるなど相続財産清算人(相続財産管理人)を選任して清算手続きを行ってもらうための法律上の利害関係が必要です。
② 相続財産があること
相続財産がほとんどない場合、費用倒れになって清算をする意味がないため、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任する必要がありません。
なお、費用倒れになるようなケースでも、申立人が費用を予納すれば、家庭裁判所は相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してくれると考えられますが、実際問題として、そこまで行う方も少ないでしょう。
③ 相続人の有無が明らかでないこと
相続人がいることがわかった場合には、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任する必要はないからです。
60分無料
2、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任は必要?ケース別に紹介
-
(1)相続人がいないケース
最初から法定相続人が誰もいない場合には、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要になります。
具体的には、以下のいずれかに該当する人がひとりもいなければ、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要です。<法定相続人になる人>- 被相続人の配偶者
- 以下のうち最上位者
- ① 被相続人の直系卑属(子ども、子どもがすでに死亡している場合には孫)
- ② 被相続人の直系尊属(父母、両親がすでに死亡している場合には祖父母)
- ③ 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合には甥・姪)
-
(2)相続人全員が相続放棄したケース
相続放棄をした人は、最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法第939条)。
もし相続権のある人全員が相続放棄をした場合、その時点で相続人はいなくなります。この場合、当初から相続人がいなかったケースと同様に、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要です。
たとえば、被相続人が多額の債務を負っていて、相続財産全体の価値がマイナスの場合は、相続人全員が相続放棄をするというようなケースが多くあります。
このような場合には、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を行わなければなりません。 -
(3)第三者への遺贈を指定した遺言書が存在するケース
被相続人が作成した遺言書により、相続人ではない人(受遺者)に対する遺贈が行われた場合、遺贈の目的物を受遺者に引き渡すことが必要です。
相続人がいるケースでは、相続人が遺贈義務者となり、受遺者に対して遺贈の目的物を引き渡します。これに対して相続人がいないケースでは、相続財産清算人(相続財産管理人)が選任された後、相続財産清算人(相続財産管理人)が受遺者に対して、遺贈の目的物を引き渡すことになります。
また、遺言書で指定されている遺言執行者が就任するケースもあるでしょう。そのようなときは、相続人の有無にかかわらず、遺言執行者が遺贈を履行する権限を有します(民法第1012条第1項、第2項)。
3、相続財産清算人(相続財産管理人)の申し立てから選任が完了するまでの流れ
-
(1)申し立てるまでの流れと必要書類
相続財産清算人(相続財産管理人)の選任は、利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して請求します(民法第952条第1項)。利害関係人に当たるのは、相続債権者・受遺者・相続放棄をした人などです。
申し立ての際には、以下の書類をそろえて家庭裁判所に提出する必要があります。申立書の記載例は裁判所のウェブサイトに掲載されているので、併せてご参照ください。<申し立てに必要となる書類>- ① 申立書
- ② 財産目録
- ③ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ④ 被相続人の父母出生時から死亡時までの、すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑤ 被相続人の子ども(およびその代襲者)で死亡している方がいるとき、その子ども(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの、すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑥ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑦ 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいるとき、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑧ 代襲者としての甥姪で死亡している方がいるとき、その甥または姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑨ 被相続人の住民票除票または戸籍付票
- ⑩ 財産目録記載の財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金および有価証券の残高がわかる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
- ⑪ 利害関係人からの申し立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書き写し等)
なお、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を申し立てる際には、必ず相続人がいないことを確認しましょう。被相続人等の戸籍謄本を調べるほか、他の相続人によって相続放棄がなされたか否かを確認することも必要です。なお、確認自体は、裁判所に照会することによって行うことができます。
-
(2)相続財産清算人(相続財産管理人)を選任した後の手続きの流れ
相続財産清算人(相続財産管理人)が選任された後は、以下の流れで手続きが進行します。
① 選任公告
相続財産清算人(相続財産管理人)を選任した家庭裁判所は、遅滞なく選任の旨と相続人がいる場合には6か月以内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません。(民法第952条第2項)。
選任公告が行われるのは、把握されていない相続人がいないかを確認するためです。もし相続人が名乗り出て相続を承認すれば、その時点で相続財産清算人(相続財産管理人)の代理権は消滅します(民法第956条第1項)。
② 相続財産の管理
相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続財産法人の法定代理人として相続財産を管理します。その際、管理すべき相続財産の目録を作成しなければなりません(民法第953条、第27条第1項)。
必要であれば、裁判所の命令に従って、相続財産清算人(相続財産管理人)が相続財産の補修、賃料の支払いなど、保存処分を行うこともあります(民法第27条第3項)。
③ 債権者・受遺者に向けた弁済申出の公告・催告
選任公告(民法第952条第2項)があったときは、相続財産清算人(相続財産管理人)は、すべての相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければなりません。(民法第957条第1項)
また、相続財産清算人(相続財産管理人)が把握している相続債権者・受遺者に対しては、個別に弁済申出の催告が行われます(民法第957条第2項、第927条第3項)。
④ 相続人の捜索の公告、債権者・受遺者への弁済
弁済申出の公告期間が満了した後、なお相続人が判明しなかった場合、家庭裁判所が相続財産清算人(相続財産管理人)または検察官の請求により、相続人の捜索の公告を行います(民法第958条)。公告期間は6か月以上に設定されます。
相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続人の捜索の公告期間が満了するまでに判明した相続債権者・受遺者に対して、それぞれ弁済を行います。また、相続人が判明して相続を承認した場合には、その時点で相続財産清算人(相続財産管理人)の代理権は消滅します。
相続人の捜索の公告期間が満了するまでに判明しなかった相続人・相続債権者・受遺者は、その権利を行使することができません(民法第958条)。
⑤ 特別縁故者への財産分与、国庫への帰属
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、相続人の捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求することが可能です。
家庭裁判所は、被相続人と特別縁故者の関係性などを考慮して、相続財産の全部または一部の分与を認める場合があります(民法第958条の2)。
特別縁故者への財産分与が完了した後、残った財産は国庫へ帰属します(民法第959条)。
⑥ 管理終了の報告
相続財産の国庫帰属が完了したら、相続財産清算人(相続財産管理人)は、家庭裁判所に対して管理終了報告を行います。これで相続財産清算人(相続財産管理人)の職務は終了です。
60分無料
4、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任するための費用は?
-
(1)申し立ての費用
相続財産清算人(相続財産管理人)選任の申し立てを行うための費用としては、申立書に貼付する800円の収入印紙、連絡用の郵便切手、官報公告料等が必要となります。
連絡用の郵便切手は1000円程度ですが、各裁判所により異なりますので、事前に申し立てを予定している裁判所に確認してください。また、予納金の納付を求められることもあります。 -
(2)予納金とは
予納金とは、相続財産清算人(相続財産管理人)の経費や報酬などに充てるため、申立人があらかじめ納めるお金のことです。
相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続財産を管理したり、債権者に支払いをしたりするため、経費が発生します。また、これら作業を専門家に依頼する場合も報酬が発生します。相続財産が少ないときは費用や報酬が不足することも考えられるため、予納金が必要です。
予納金の金額は、事案に応じて裁判所が決めます。100万円などという金額になることもある点に留意してください。
相続の処理が終わり、その後に費用の精算と報酬の支払いが完了しても予納金に残りがある場合には、返金されます。
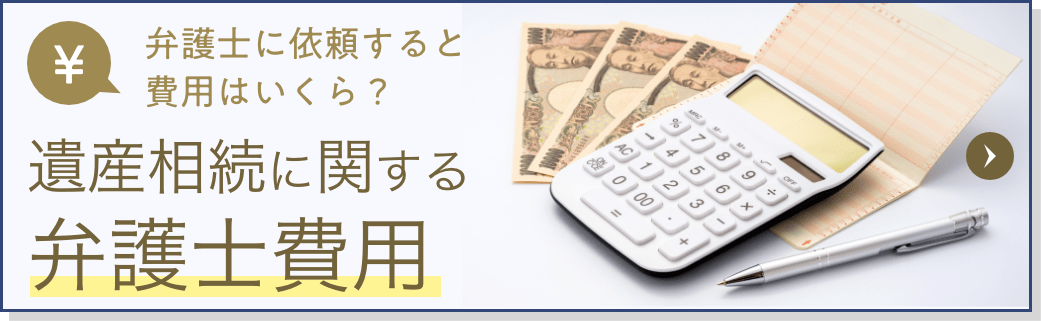
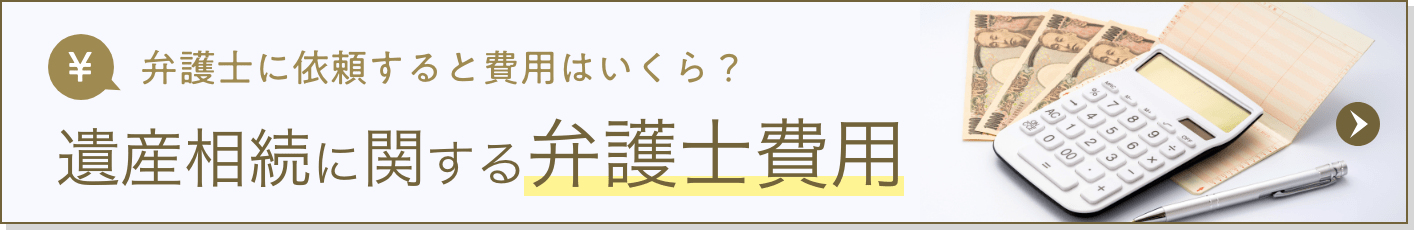
5、まとめ
相続財産清算人(相続財産管理人)制度は、亡くなった方(被相続人)に相続人がいないことに伴い、何かしらの不都合があるときに活用されるものです。
たとえば相続人がいない、あるいは相続人がいても相続放棄するという場合、相続債権者が弁済を受けるなどのためには、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を行いましょう。
ただ、相続財産清算人(相続財産管理人)の申し立てには、多数の提出書類が必要であり、手続きも複雑なので非常に手間が掛かります。時間や手間を考えると、弁護士や司法書士などに依頼するのが合理的といえるでしょう。
ベリーベストグループには、弁護士のほか、税理士や司法書士も在籍しており、相続全般について相談・依頼をすることが可能です。遺産相続についてお悩みがある場合には、お気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)
-
2025年06月25日
- 遺産を受け取る方
- 家督相続とは

戸主(戸籍の代表者)が亡くなった際に、長男がすべての遺産や権利を受け継ぐ「家督相続」の制度は、現在の民法では廃止されています。
しかし、他の相続人が「自分は長男だから」とすべての相続財産を得るような発言をした際に、「家督相続の制度は廃止されている」と訴えても、決着がつかないケースもあるでしょう。
本コラムでは、家督相続を主張してくる相続人への対処法や、現在の遺産相続の基本的なルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
2025年06月19日
- 遺産を受け取る方
- 死後離縁

死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年06月16日
- 遺産を受け取る方
- 名寄帳とは
- 請求できる人
- 不動産

ご家族が亡くなり、遺産相続が発生した場合、遺品などの整理とともに相続財産の調査をしなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の預貯金や有価証券、不動産、貴金属、さらに借金の情報は、遺産分割を行うために必要です。また、相続税の申告の要否や税額を判断するための情報にもなります。
相続財産に不動産がある場合は、市区町村が作成する「名寄帳(なよせちょう)」をもとに確認するのが一般的です。権利証や毎年送付される固定資産税に関する課税明細書でも不動産の情報を知ることができますが、見落としが起きないよう、名寄帳を利用しましょう。
本コラムでは、名寄帳とはどういうものか、不動産の調査のために名寄帳の取得が推奨される理由や名寄帳を請求できる人と取得方法、相続財産の調査が不十分だった場合に起きる問題などについて、ベリーベスト法律律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 相続財産清算人(相続財産管理人)とは? 役割や流れ、費用を解説


















