遺産相続コラム
-
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 計算
更新日:2026年01月07日 公開日:2026年01月07日
生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 隠し子
- 相続
更新日:2025年12月15日 公開日:2025年12月15日
親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。
結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。
今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- マンション
- 相続
更新日:2025年12月11日 公開日:2025年12月11日
マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 被相続人とは
更新日:2025年11月27日 公開日:2025年11月27日
被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 離婚した親の相続
更新日:2025年11月19日 公開日:2025年11月19日
顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 遺言書
- 全財産
- 無効
更新日:2025年10月15日 公開日:2025年10月15日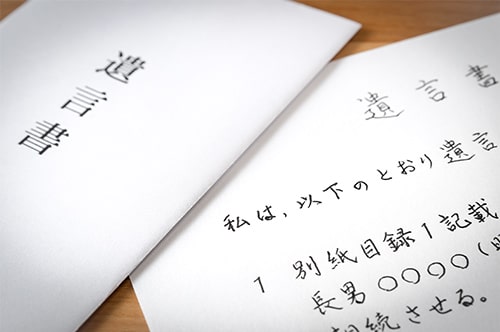
「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 除籍謄本とは
更新日:2025年10月07日 公開日:2025年09月29日
除籍謄本とは、戸籍に記載されていたすべての人が除かれた後の戸籍の写しです。
日常生活ではほとんど利用することのない書類ですが、相続手続きにおいては法定相続人を確定するために重要な書類です。特に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する際には、除籍謄本の取得が必要になります。
本記事では、除籍謄本とは何か、戸籍謄本や改製原戸籍との違い、取得方法、注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 遺産相続
- 寄与分
- 相場
更新日:2025年10月01日 公開日:2025年09月17日
亡くなった家族の事業を手伝っていた場合や、介護を献身的に行っていた場合などには「寄与分」が認められ、相続分を増やせる可能性があります。
寄与分を主張したいときは、適切な手続きを踏み、場合によっては家庭裁判所での審判を行います。適正額の寄与分を受けるためには、弁護士に相談することも検討しましょう。
本記事では、寄与分と特別寄与料の違いや寄与分の相場と計算方法、寄与分を主張する際の手続きや注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 再転相続
更新日:2025年10月01日 公開日:2025年09月11日
法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。
再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。
今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 特別代理人
更新日:2025年08月07日 公開日:2025年08月07日
親子がともに相続人となる場合など、遺産分割に当たって特別代理人の選任が必要となるケースがあります。
特別代理人の選任が必要かどうか分からない場合や、選任申し立ての手続きについて不安な点がある場合は、弁護士のアドバイスを受けましょう。
本記事では特別代理人について、遺産相続の場面における役割や必要となるケース、選任申し立ての手続きなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 兄弟
- 相続
更新日:2025年07月31日 公開日:2025年07月31日
兄弟姉妹が亡くなった場合にご自身が遺産を相続できるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹も法定相続人の範囲に含まれていますので、一定の条件を満たした場合は、兄弟姉妹も遺産を相続することが可能です。
ただし、兄弟姉妹の相続では、税金、代襲相続、遺留分など注意すべきポイントがいくつかありますので、兄弟姉妹の相続に備えて必要な知識を身につけておきましょう。
今回は、兄弟姉妹の相続における相続順位、兄弟姉妹が遺産を相続できるケース、兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求
- 調停
更新日:2025年07月23日 公開日:2025年07月23日
生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- 死因贈与
更新日:2025年07月23日 公開日:2025年07月17日
贈与者が亡くなったことを条件とする贈与を「死因贈与」といいます。
死因贈与は遺言書による贈与(=遺贈)に似ていますが、実際は異なるものです。それぞれの特徴を踏まえたうえで、適切な方法を選択しましょう。
本記事では死因贈与について、遺贈との違いやメリット・デメリット、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約
更新日:2025年07月09日 公開日:2025年07月09日
将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。
財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。
一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。
本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 家督相続とは
更新日:2025年06月25日 公開日:2025年06月25日
戸主(戸籍の代表者)が亡くなった際に、長男がすべての遺産や権利を受け継ぐ「家督相続」の制度は、現在の民法では廃止されています。
しかし、他の相続人が「自分は長男だから」とすべての相続財産を得るような発言をした際に、「家督相続の制度は廃止されている」と訴えても、決着がつかないケースもあるでしょう。
本コラムでは、家督相続を主張してくる相続人への対処法や、現在の遺産相続の基本的なルールなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分減殺請求
更新日:2025年07月17日 公開日:2025年06月23日
遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。
遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。
本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 死後離縁
更新日:2025年07月14日 公開日:2025年06月19日
死後離縁とは、普通養子縁組をした当事者である養親または養子が死亡した後、養子縁組を解消する手続きです。
死後離縁をすると法律上の親子関係や親族関係が解消されますが、すでに起こった相続には影響はないため、死後離縁前に相続人であった養親・養子は、死後離縁後も相続権を維持します。思わぬ相続トラブルを防ぐためにも、死後離縁を検討する際はしっかりと制度を理解したうえで行うようにしましょう。
今回は、死後離縁の概要や手続き、メリット・デメリットなど、死後離縁に関する相続トラブルを防ぐ方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 生前贈与
- 独り占め
更新日:2025年07月07日 公開日:2025年06月18日
被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。
このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 同時死亡の推定
更新日:2025年03月19日 公開日:2025年03月19日
交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 相続登記
- 相続
- 登記
- 必要書類
更新日:2025年04月16日 公開日:2025年03月12日
相続財産に不動産が含まれる場合、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義へと名義変更が必要になります。これを「相続登記」といい、令和6年4月1日から、申請が義務化されました。
相続登記には、さまざまな書類が必要になり、準備すべき書類は、遺産相続のケースに応じて異なります。期限までに相続登記を終えるためにも、ご自身の状況でどのような書類が必要になるかをしっかりと押さえておくようにしましょう。
今回は、相続登記の必要書類や取得方法、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。















