- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
遺産相続コラム
-
- 遺産を受け取る方
- 実家
- 相続
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年12月19日
両親が亡くなった後に、実家の土地や建物をどう相続するかは、多くの方にとって悩ましい問題です。
たとえば、思い入れのある実家を残したいと思っても、誰か住むのかで揉めてしまうケースや、相続後の管理に多大な労力を要するケースが少なくありません。
実家の土地や建物が相続財産にある場合は、各選択肢のメリット・デメリットを踏まえて、家族にとってどのような形が望ましいかをよく検討しましょう。
本コラムでは、実家の土地や建物を相続する際の基礎知識や手続きの流れ、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 原戸籍とは
更新日:2025年07月23日 公開日:2023年12月12日
遺産相続が始まると、手続きを進めるなかで、原戸籍(改製原戸籍謄本)の提出を求められる場合があります。
多くの方にとって原戸籍はなじみがない言葉であり、「原戸籍とは、どういう書類?」「相続手続きのどの場面で必要?」と、疑問を抱えている方も少なくないでしょう。
本コラムでは、原戸籍と戸籍謄本の違いや手続き方法、取得方法、また、原戸籍が必要な相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺言
- 負担付遺贈
更新日:2023年12月05日 公開日:2023年12月05日
負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。
ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。
本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 相続登記
- 相続人申告登記
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年11月21日
令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まりました。義務が発生するのは4月1日以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になります。
そのため、期限までに相続登記を終えなければ過料の制裁を受けるリスクがあるため、注意が必要です。
こうした制裁リスクを回避できるように新しく創設された制度が、「相続人申告登記」です。
相続登記をするには、遺産分割協議で遺産の分配を決める必要がありますが、期限内に遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースもあるでしょう。そのようなときに、この相続人申告登記の制度を利用することで、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになりました。
本コラムでは、相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 特別縁故者
更新日:2025年04月24日 公開日:2023年11月02日
亡くなった方(被相続人)に相続人が誰もいない場合、その方の遺産はどうなってしまうのだろうかと疑問に思っている方もいるでしょう。ひとりも相続人がいない方の遺産は、最終的に国のものになります。
しかし、特別縁故者と認められれば、遺産の全部または一部をもらうことが可能です。相続人には含まれない内縁の配偶者、いとこ、介護人なども、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
本コラムでは、特別縁故者の要件や財産分与を受けるときの流れなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 土地の相続
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年10月16日
相続財産に土地が含まれている場合、立地や用途によって相続したほうがよいのだろうかと悩むケースは少なくありません。
住居用の土地を相続すれば、自宅を建てたり第三者に貸し出したりできるなどのメリットがありますが、土地によっては活用が困難で、管理や税金負担などのデメリットもあります。
また預貯金と違い、土地の分割を公平に行うのは難しいことも多く、相続人間で争いを起こさないためには、慎重に進めることが大切です。
本コラムでは、土地の相続におけるメリット・デメリット、相続人間で土地を分割する方法、相続登記や相続しない場合の手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 相続放棄・限定承認
- 財産放棄
更新日:2023年09月21日 公開日:2023年09月21日
被相続人(亡くなった方)の遺産を相続したくないけれど、どうしたらよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。検索すると、「相続放棄」や「財産放棄(遺産放棄)」といった言葉が出てくるものの、それぞれどういうことなのか分からず、進め方も分からないという方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」はその名前は似ていますが、まったく異なるものです。被相続人の遺産を相続しない場合、それぞれの効果を踏まえて適切な手続き方法を選択しなければ、思いもよらぬトラブルに発展してしまうことがあります。
本コラムでは、相続したくないものがある場合にどうしたらよいのか、相続放棄や財産放棄(遺産放棄)をする方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 未登記建物
- 相続
- 遺産分割協議書
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年09月14日
不動産に関する相続手続きのなかでも、特に問題となりやすいものが「未登記建物」です。未登記建物を相続する場合、遺産分割協議書の作成には、十分に注意しましょう。
本コラムでは、未登記建物の相続に関わる問題点や遺産分割協議書の作成方法など、一連の相続手続きにおける未登記建物の取り扱いについて、相続業務を幅広く取り扱っているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
なお、表題部の記載のみで、所有権保存登記などの権利部の記載がない建物は、多数存在しているのが実情です。そして、そのような建物も未登記建物と呼ばれることもありますが、本コラムでは、表題部すらない未登記建物に限定して説明します。 -
- 遺産分割
- 異母兄弟
- 相続
更新日:2025年08月25日 公開日:2023年09月07日
異母兄弟・異父兄弟がいるとき、相手との面識がない・不仲であるなど、何かしらの問題を抱えている方は少なくありません。そのため、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続は、トラブル発生のリスクが高まります。
そもそも、亡くなった方(被相続人)の遺産について、異母兄弟や異父兄弟とどのように分け合えばよいのか、相続順位や相続分はどうなるのか、慣れない対応を進めるのに多くの疑問点もあるでしょう。
本コラムでは、異母兄弟・異父兄弟の相続に関して、民法のルールやトラブル例、注意点など、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 父死亡
- 母
- 認知症
- 相続
更新日:2025年07月17日 公開日:2023年08月29日
父親が亡くなり、遺産相続が始まった際は、遺産(相続財産)の分割について相続人間で話し合う必要があります。
しかし、母親が高齢で認知症にかかっているケースでは、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。協議を進行するためには成年後見制度の利用を申し立てなければなりませんが、後見人等による横領のリスクには十分注意が必要です。
本コラムでは、父親が死亡し、母親が認知症にかかっている場合における相続手続きの注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 遺産分割協議
- やり方
更新日:2025年04月21日 公開日:2023年08月17日
身内の方が亡くなり、相続が発生したものの、どのような方法で遺産を分ければよいのかわからないという方も多いと思います。遺産相続は、頻繁に経験することではありませんので、手続きを熟知しているという方はほとんどいないでしょう。
複数の相続人がいるケースにおいて遺産を分けるときは、相続人による遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺産分割協議をする前提として、事前にさまざまな調査を行わなければなりません。
本コラムでは、初めて遺産分割を行うことになった方でも理解できるように、遺産分割協議の流れをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 相続手続き
- 自分で
更新日:2025年04月16日 公開日:2023年08月08日
ご家族が亡くなった場合、相続手続きに関する対応が必要になります。
相続手続きは、専門的知識を必要とするため、相続人が自分で対応するのは非常に困難です。特に、今回初めて相続手続きをするという方は、どのように相続手続きを進めたら良いのかわからず、戸惑ってしまうのではないでしょうか。
相続手続きの全体像を把握したうえで、「自分で対応するのは難しい」と判断した場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。本コラムでは、相続手続きを自分で行う際の手順や、自分で相続手続きを進めるのが難しいケースやリスク等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 失踪宣告
- 相続
更新日:2025年04月16日 公開日:2023年07月18日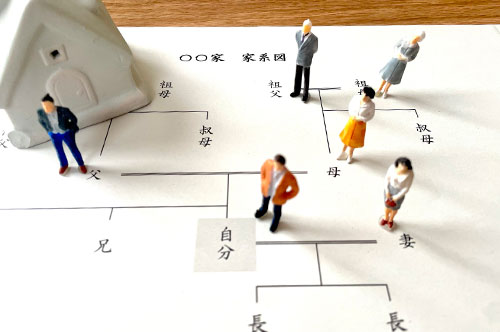
行方不明になっている相続人がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
行方不明の期間が長期間にわたる場合には、不在者財産管理人の選任申し立てのほか、失踪宣告を申し立てる方法も考えられます。失踪宣告の申し立ては、法律上多くの注意点が存在するため、弁護士にご相談ください。
今回は、長期間行方不明の相続人がいる場合の対処法となる「失踪宣告」について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 相続財産清算人
- 相続財産管理人
- 相続人がいない
更新日:2025年11月26日 公開日:2023年07月11日
亡くなった方(被相続人)が独身で、子どもや親兄弟がおらず法定相続人に該当する人がいない場合や、法定相続人がいても全員が相続放棄をするような場合は、相続財産(遺産)を管理する人がいないことになります。
相続人がいないことに伴う不都合があるときには、家庭裁判所に申し立てを行って、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任してもらいましょう。
本コラムでは、相続財産清算人(相続財産管理人)制度の概要や必要になるケース、選任申し立ての方法や流れ、費用について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 遺産隠し
- 横領
- 対処法
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年07月03日
亡き親の遺産である預貯金を調べていると、親の死亡前後に不自然な出金があることに気付くケースがあります。
そのような場合、親と同居していた人物によって、遺産が不正に使い込まれていたのではないかと疑うこともあるでしょう。
本コラムでは、遺産隠しや横領などによって使い込まれた際の遺産を取り戻す方法や、「怪しい」と思ったときにとるべき行動などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 遺産分割協議書
- 騙された
更新日:2023年06月20日 公開日:2023年06月20日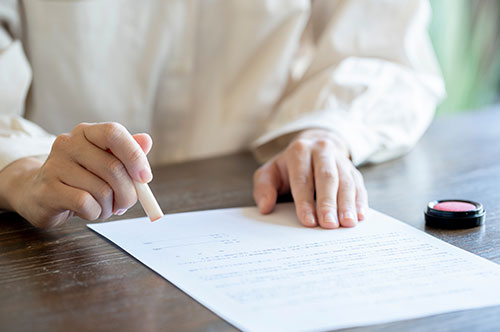
遺産分割協議書に署名・押印をしたものの、後日、他の相続人に騙されていたことが判明した場合、どうすればよいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このようなケースでは、遺産分割協議の取り消しを行い、遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。
ただし、遺産分割協議を取り消すことができるのは、あくまでも例外的なケースに限られますので、どのような場合に取り消しや無効を主張することができるのかをしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、遺産分割協議書の作成後に騙されていたことが発覚した場合の対処法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 親子
- 共有名義
- 片方
- 死亡
- 相続
更新日:2025年04月21日 公開日:2023年06月15日
親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。
親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。
また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺留分侵害額請求
- 公正証書遺言
- 遺留分
更新日:2025年07月07日 公開日:2023年05月30日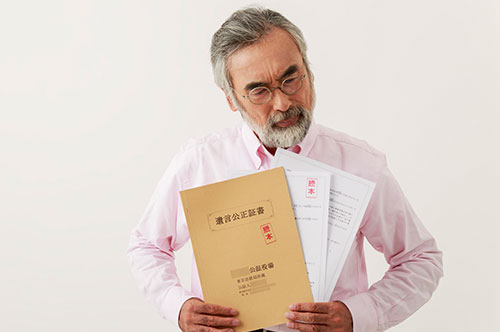
遺言書によって指定された相続分があまりにも偏っていた場合には、相続人同士で「遺留分侵害額請求権」が争われる可能性があります。
遺産相続においては、たとえ公正証書遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていたとしても、他の相続人に認められている「遺留分」を侵害する部分について遺留分侵害額請求として金銭請求されることになります。
もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切にトラブルを解決するため、弁護士に相談することをおすすめします。本コラムでは、遺留分と公正証書遺言の関係や、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続き・対応・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産分割
- 遺産
- 相続
- 長男
- 独り占め
更新日:2025年07月02日 公開日:2023年05月09日
父親が亡くなると「母の面倒は僕が全部みるから」などと言い出して、実家の不動産や現金・預金など、すべての遺産を長男が独り占めにしようとするケースがあります。
あるいは、面倒を見ていなかったのに「長男だから」という理由で、不公平な分配を主張してくるケースもあるでしょう。
このようなとき、「特定の相続人が遺産を独占する主張は、法的に通用するのだろうか」「親の遺産相続で財産を独り占めされたくない」などと考える方は少なくないはずです。
本コラムでは、親の遺産相続で長男が財産をすべて独り占めしようとするとき、将来的に想定されるリスクや注意点、相続トラブルの対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 相続放棄
- 土地
- 農地
- 山林
更新日:2025年07月17日 公開日:2023年04月18日
被相続人(亡くなった方)の相続財産に農地や山林などの用途が限定される土地が含まれており、どうしようかと悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続は、相続人にとって必ずしもプラスになるとは限りません。農地や山林といった相続する土地の種類によっては、むしろマイナスの資産となる可能性があります。
マイナスの資産を相続して不利益を被る前に、土地の価値を事前にしっかりと見極め、場合によっては相続放棄などを検討しましょう。
本コラムでは、相続人にとって不要な土地となりやすい農地や山林の特徴を交えながら、マイナスの資産となってしまう土地を背負い込まないよう、相続放棄を行うときの手続きや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム















