- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
遺産相続コラム
-
- 遺産分割協議
- 生前贈与
- 土地
- 兄弟
更新日:2025年07月02日 公開日:2020年06月02日
兄弟のうち、ひとりだけが生前贈与を受けて、土地などの不動産や現金を取得していることがあります。生前贈与を内緒にしていたことに対して、他の相続人は「自分の取り分が少なくなることに納得できない」と、憤りや不公平に感じるケースがあるでしょう。
一定の相続人は、「遺留分」と呼ばれる相続財産の最低限の取り分が民法上、認められています(民法1024条)。
したがって、自分の最低限の相続財産を侵害された場合には、遺留分を主張することで適切な相続分の支払いを請求することが可能です。
本コラムでは、遺留分や生前贈与の基本的な知識をはじめ、特別受益や遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れになどついて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺言
- 遺言書
- 無効にしたい
- 見分け方
更新日:2025年07月02日 公開日:2020年05月26日
遺言書は、亡くなった方(被相続人)の意思が書かれたものなので、有効な遺言書があればそのとおりに遺産を分けなくてはなりません。遺産は元々亡くなった方の所有物だったことから、その処分も亡くなった方の意志に従うのが理にかなっているとされているのです。
しかし、「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書を無効にしたい」「遺言書の内容を無視して遺産を分配したい」という相続人もいるでしょう。
まず、遺言書が存在していても、法律上効力を認められない遺言であるために、効果が生じない(無効になる)場合があります。法的に意味がないということは、そもそも遺言がされなかったということと変わらず、遺言書を無視して遺産分割を行うことに問題はありません。
遺言書が有効であったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。
本コラムでは、有効・無効な遺言書の見分け方や、有効な遺言書があっても遺言書の内容と異なる内容の遺産分割をしたい場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 海外
- 相続
更新日:2025年04月18日 公開日:2020年05月19日
親の相続が発生したとき、遺産に「海外資産」が含まれていたらどのように対応すれば良いのかと、不安に思う方も少なくありません。
相続財産に海外不動産などがある場合、日本国内にある資産と取り扱いが異なる可能性があります。このように海外の財産を相続するケースを「国際相続」ともいいます。
本コラムでは、海外資産の相続方法や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺言
- 相続させる旨の遺言
- 遺言書
更新日:2023年09月08日 公開日:2020年05月12日
自分の遺産を自分の意思で相続させる方法として「遺言」があることは多くの方がご存じだと思いますが、財産の分配方法について遺言でどこまで指定できるのかご存じでしょうか。
自分の死後、子どもたちが相続でもめないようにするために、特定財産を特定の個人に分配できないかと考えている方も多いと思いますが、「遺言についてどう書いていいかわからない」という方がほとんどでしょう。
そこで、今回は、特定の個人に特定の財産を相続させる場合の遺言の注意点について解説していきます。 なお、以下では「相続財産」、「遺産」という言葉が出てきますが、いずれも同じ意味で使用しています。 -
- 遺産を受け取る方
- 代襲相続
- 遺留分
- 相続放棄
更新日:2023年09月08日 公開日:2020年04月28日
代襲相続人として受け継ぐ相続財産の中に借金などの負債がある場合、相続放棄を検討する方も少なくありません。
その際には次順位の相続人に相続権が移動しますが、事前に話し合いや連絡をせずに相続放棄を行った場合は、トラブルに発展する可能性があります。
相続の中でも、「代襲相続」が絡むケースでは相続問題が複雑化にすることも多く、手続きは注意を払って進める必要があります。
本コラムでは、代襲相続人の範囲や代襲相続したくない場合の基礎知識を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- おひとりさま
- 相続
更新日:2023年09月08日 公開日:2020年04月21日
内閣府の発表によると、未婚率は年々上昇しており、出生率も下がり続けています。また、結婚をしても子どもがおらず伴侶と死に別れて、いわゆる「おひとりさま」生活を続けているという方も少なくありません。このように、おひとりさまは日本社会の中で増え続けており、珍しいことではなくなってきました。
しかし、親族や身内が誰もいない、兄弟姉妹とは没交渉になっている、甥や姪とは冠婚葬祭や年賀状のやり取りしかしていないといった状況では、自分が死んだ後の遺産が誰に相続されるのか不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本コラムでは、おひとりさまの遺産はどのように相続されるのか、相続で後々揉めないために生前にできる対策にはどのようなものがあるのかについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 相続税対策
- 相続税
- 控除
更新日:2025年04月21日 公開日:2020年04月14日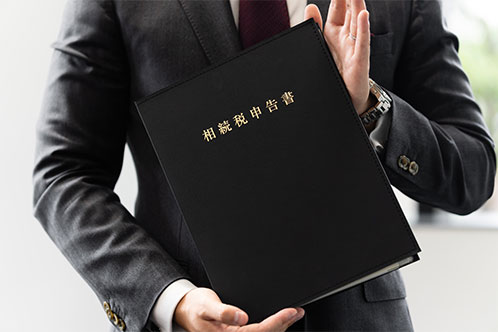
遺産を相続したとき、財産総額が一定以上になっていると相続人は「相続税」を申告・納付しなければなりません。
税額が大きくなると手元に残る遺産が減ってしまいますが、相続税は控除などを利用して節税できる可能性があります。
本コラムでは、相続税の基本的な計算方法と控除の制度について、ベリーベスト税理士事務所の税理士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
更新日:2023年09月22日 公開日:2020年04月07日
令和2年4月から「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が新たに施行されました。この2つの制度は被相続人(亡くなった方)の配偶者に経済的な恩恵があるだけでなく、今後の相続税対策にも影響が出るものと考えられます。
そこで本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の概要について、ベリーベスト法律事務所の遺産相続専門チームの弁護士がわかりやすく解説します。 -
- 遺産を残す方
- 特定遺贈
- 包括遺贈
- 遺贈
更新日:2023年09月08日 公開日:2020年03月31日
相続人以外に財産を相続させたいと考えているけれど、具体的にどうすればいいのかお悩みの方も少なくありません。そういった場合に用いられる方法として、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
本コラムでは、遺贈の意味や、特定遺贈と包括遺贈の違い、それぞれのメリット・デメリットなど、遺贈を悩んでいる方のために、弁護士が解説いたします。 -
- 遺産分割協議
- 換価分割
更新日:2025年04月18日 公開日:2020年03月24日
遠方の田舎などにある実家を相続すると、所有し続けるのが負担になるケースが多々あります。
そのようなとき、実家を売却して相続人間で売却金を分ける方法があることをご存じでしょうか。このように現物の財産を売却してお金で分ける遺産分割の方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。
本コラムでは、換価分割の流れや換価分割が適しているケース、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産分割協議
- 不在者財産管理人
- 選任
- 遺産分割協議
更新日:2025年04月16日 公開日:2020年03月10日
相続人が複数いて、遺言がない場合、遺産について相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をすることとなります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そうすると、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人全員で行うべき遺産分割協議ができないことになります。しかしながら、それではいつまでたっても相続ができないことになります。そんなときには、行方不明の相続人の代理として、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を選任することで、遺産分割協議を行うことができます。
そこで、本コラムでは、不在者財産管理人の役割や権限をはじめ、選任するときに留意すべき点などについて解説したいと思います。 -
- 遺産を残す方
- 孫
- 遺産
- 相続
- 遺産相続
- 相続権
- 相続人
更新日:2025年07月02日 公開日:2020年02月12日
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 相続
- もめる
- トラブル
- 弁護士
更新日:2025年07月07日 公開日:2020年01月21日
平成30年、全国の家庭裁判所では遺産の分割に関する処分などを求める調停、いわゆる遺産分割調停が1万3739件受理されています。
これは基本的に遺産相続をめぐるトラブルの件数と考えてよいでしょう。
被相続人が亡くなったことの悲しみが癒えないなか、その遺産をめぐって家族や親族ともめることなど、誰もが避けたいところです。
特にさまざま事情で遺産を法定相続割合で平等に分けることが難しい場合の遺産分割協議(遺産を誰が・何を・どの割合で相続するか相続人どうしで話し合って決めること)は、仲のよい関係にある人ほどもめることもあります。それがきっかけで、もっとも大事な家族や親族との関係が失われてしまうこともあります。
そこで本コラムでは、遺産をめぐり家族や親族ともめることになってしまった場合、もめる原因は何が考えられるのか、そして解決するための最善の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 株
- 株式
- 相続
更新日:2025年07月02日 公開日:2019年12月17日
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和6年(2024年)7月に発表した「2023年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は7445万人(前年度比462万人増)で10年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 土地
- 相続
更新日:2023年09月21日 公開日:2019年12月10日
数多くの相続事例を振り返りますと、土地などの不動産が相続財産評価額に占める割合は高い傾向があります。
土地は現預金や有価証券などの金融資産と異なり個別性が強く、土地の種類や相続人の状況に応じて相続手続きに時間がかかりやすい資産です。また、土地を相続したあとは固定資産税や管理責任が発生するため、場合によってはコストだけかかる「負動産」を抱え込むリスクもあります。
したがって、土地を相続するときは相続後の利用方法をどうするか、そもそも相続するべきか、さまざまな検討が必要になってきます。
そこで、相続財産に土地が含まれている方が今後のために知っておくべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺言
- 遺言執行者
- 遺言
- 選任
更新日:2023年09月22日 公開日:2019年12月03日
ご自身の死後、遺産の配分などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している人は数多くいます。
しかし、せっかく遺言書を作成していたとしても、遺言の内容の実現に反対する相続人の抵抗などにより、遺言書の内容が円滑に実現しないのであれば意味はありません。
そのような事態をできる限り軽減するための一つの方法として、生前に遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。遺言執行者には、あなたが亡くなり相続が発生しても、遺言書にしたためたあなたのご遺志を実現するための役割が期待できます。
このコラムでは、遺言執行者がもつ権限や相続において果たす役割などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
- 遺産を残す方
- 養子縁組
- 解消
- 相続
- 手続き
更新日:2025年07月02日 公開日:2019年11月12日
裁判所が公開する令和5年の「司法統計」によると、特別養子縁組の成立は1006件の受理、養子縁組解消(離縁)に関する処分は1件の受理となっていました。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。養子縁組が行われるケースとして結婚相手に連れ子がいるときが例に挙げられますが、もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
- 遺産を受け取る方
- 共有名義
- 不動産
更新日:2023年09月21日 公開日:2019年11月05日
自身が父や母などの財産を相続するとき、遺産の中に「共有名義の不動産」が含まれていると、さまざまなトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
共有名義とは、兄弟や家族、知人友人など複数の人間が共同でその物を所有している状態ですが、なぜ共有名義の不動産がトラブルになりやすいのでしょうか?
もし、共有名義の不動産を相続してしまったら、どのように対処するのが良いのでしょうか?
今回は、相続財産に共有名義の不動産があるケースにおいて、トラブルを避けつつスムーズに相続する方法を弁護士がご説明します。 -
- 遺産を受け取る方
- 連帯納付義務者
- 相続税
更新日:2023年09月20日 公開日:2019年10月29日
すでに自分は相続税を納付したのに、税務署から「連帯納付義務制者」として相続税を納付していない他の相続人の分まで相続税を支払えと督促処分を受けてしまった……。理不尽な話ですが、相続税の「連帯納付義務制度」により、このようなことは起こり得るのです。
なぜ、連帯納付義務制者は他の相続税納税義務者の分まで支払わなければならないのでしょうか? そもそも連帯納付義務制度とはどのようなものなのでしょうか?
本コラムでは、このような疑問について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -
- 遺産を残す方
- 相続
- 欠格
- 廃除
更新日:2023年09月08日 公開日:2019年10月08日
本来、法定相続人の立場であっても「相続欠格者」になると相続する資格がなくなります。どのような場合に相続欠格者となるのか、推定相続人の廃除とはどう違うのか、また相続人の中に相続欠格者がいると、どのようにして遺産相続手続を進めていけば良いのでしょうか? 以下で相続欠格について、弁護士が詳しく解説していきます。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム















