- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を残す方
- 遺留分対策に生命保険金は活用できる!? 例外ケースと相続対策
遺産相続コラム
遺留分対策に生命保険金は活用できる!? 例外ケースと相続対策
- 遺産を残す方
- 遺産相続
- 遺留分
- 生命保険
- 相続対策

遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。「特定の相続人に多くの財産を渡したい」「相続人同士揉めないようにしたい」とお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、生命保険金と遺留分
1章では、遺留分とはどのような制度なのか、また遺産分割において生命保険金はどのように扱われるのか、生命保険金と遺留分との関係について説明します。
-
(1)遺留分とは
遺留分とは、法律上、兄弟姉妹以外の相続人に保障された一定割合の遺産のことをいいます。
民法では、法定相続人には、遺産の取得割合として法定相続分が規定されています。しかし、被相続人(亡くなった方)が遺言によって法定相続分とは異なる割合で遺産を分配することも認められていますので、特定の相続人にすべての遺産を相続させるという内容の遺言も有効です。
しかし、このような遺言がなされた場合には、他の相続人が受け取る財産は、その相続人に保障されている遺留分に満たないことになります。そのため、遺言の内容に不満のある相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。 -
(2)生命保険金は遺産には含まれない
被相続人の死亡によって、相続人のうちの一人が高額な死亡保険金(生命保険金)を受け取った場合には、他の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができるのでしょうか。
生命保険契約は、保険契約者が保険会社に対して保険料を支払うことにより、特定の人の死亡という保険事故が発生した場合に、保険会社が保険金受取人に対して生命保険金を支払うという内容の契約です。そうすると、そもそも保険会社に対する生命保険金請求権(生命保険金)が遺産に含まれるかどうか、を考える必要があります。
死亡保険金(生命保険金)は、被相続人の死亡によって支払われるお金ですので、遺産に含まれると思っている方も多いかもしれません。しかし、原則として、生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。
なぜならば、生命保険金は、保険会社から保険金受取人に対して支払われるものですので、被相続人の財産ではなく、保険金受取人固有の財産として扱われます。
このように、生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれないため、遺留分の対象にもなりません。
そのため、特定の相続人に多くの財産を渡したいという場合には、当該相続人を保険金受取人として指定した生命保険契約を利用することによって、他の相続人の遺留分を心配することなく希望を実現することが可能です。
なお、相続人が受け取る生命保険金には、相続税または贈与税が課税される可能性があります。そのため、生命保険金を特定の相続人に渡したいときは、税金についても考慮しなくてはなりません。
2、生命保険金が遺留分の対象となる例外ケース
生命保険金は、上記のとおり、原則として遺産に含まれず遺留分の対象にはなりませんが、例外的に遺留分の対象になるケースもあります。
判例では、生命保険金を受け取った相続人とそれ以外の相続人との間で著しい不公平が生じる場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断しています(最高裁平成16年10月29日判決)。
特別受益とは、相続人が遺贈または贈与により被相続人から受けた利益をいいます。生命保険金を特別受益に準じて持ち戻しの対象にするということは、遺留分を算定するための遺産の価額に生命保険金を加えることを意味しますので、遺留分権利者の取得する遺留分が増えることになります。
具体的には、以下の事情等を総合考慮した結果、著しい不公平が生じる場合には、他の相続人から生命保険金が遺留分算定の基礎となる財産に含まれるとの主張をされるリスクが生じるでしょう。
- 生命保険金の金額
- 生命保険金の遺産総額に対する比率
- 生命保険金の受取人及び他の共同相続人と被相続人との関係
- 各相続人の生活実態
たとえば、被相続人の遺産が1000万円、生命保険金が1億円であったという場合には、遺産総額に占める生命保険金の割合が大きいと考えられます。生命保険金の受取人が被相続人の介護に貢献していたなどの特別な事情がない限りは、特定の相続人だけが高額な生命保険金を受け取ることは著しく不公平といえますので、生命保険金が遺留分算定の基礎となる財産に含まれる可能性が高いでしょう。
60分無料
3、生前からできる遺留分・相続対策
生命保険金の有無にかかわらず、遺産相続はそもそもトラブルが生じやすいといえます。特に、相続人同士が不仲である場合や、被相続人と特定の相続人が不仲である場合は、相続争いが一層生じやすいでしょう。
相続争いを防止するためには、生前に以下のような相続対策を講じておくことが大切です。
-
(1)遺留分の放棄
遺留分の放棄とは、相続人が自らの意思によって遺留分権を放棄することをいいます。遺留分は、相続人の遺産に対する期待を保護するために認められている制度ですので、相続人自身がその利益を放棄することは可能です。なお、遺留分の放棄は、相続の放棄とは異なりますので、被相続人が死亡して相続が開始した後に相続人となることに変わりはありません。
このように遺留分の放棄は、相続人自身が行うものですので、相続人に遺留分の放棄をしてもらうためには、当該相続人が納得してくれるような条件を提示しなくてはなりません。そこで、被相続人が死亡したときの生命保険金の受取人を当該相続人に指定し、その交換条件として遺留分の放棄をしてもらうという方法が考えられます。
たとえば、家業を継いでいる長男に対して相続財産に含まれる不動産を渡したいが、次男の遺留分を侵害してしまう、という場合は、次男を生命保険金の受取人に指定する代わりに、遺留分を放棄するよう、次男に求めることが考えられます。
ただし、被相続人や他の共同相続人らによる不当な働きかけを防止するために、被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所による許可を得る必要があります。家庭裁判所では、遺留分の放棄をする相続人の自由意思、放棄理由の合理性や必要性、放棄と引き換えの代償の有無などを考慮して拒否が判断されますので、必ず許可されるわけではない点に注意が必要です。
また、不仲な相続人に対して遺留分の放棄を求めても拒否される場合がありますが、当該相続人に対して遺留分の放棄を強要することはできませんので注意しましょう。 -
(2)生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前に相続人へ財産を渡すことをいいます。たとえば、財産をできる限り渡したくない相続人がいる場合、生前贈与の活用がおすすめです。
特定の相続人へ計画的に財産を渡していくことで、将来の相続財産を減らし、財産を渡したくない相続人の遺留分を減らすことができます。
ただし、相続人に対する生前贈与については相続開始前の10年間にしたもの(なお、相続人以外の第三者に対して生前贈与した場合には相続開始前の1年間にしたものに限る。)については、遺留分を算定のための財産の価額として考慮することとなりますので、相続人に対して生前贈与を行う場合には、長期計画を立てて生前贈与を行う方がよいでしょう。
また、生前贈与は、相続税対策としても有効です。
被相続人が死亡した場合には、被相続人の相続財産に応じて相続税が課税されます。相続税には、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)がありますので、相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合には、相続税を納めなくてはなりません。
そこで、生前贈与によって、相続時の相続財産の総額を減らすことで、負担する相続税を減らすという方法が考えられます。
生前贈与の場合には、受贈者側に贈与税が課税されることになりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、毎年110万円までの贈与を繰り返すことによって、贈与税の負担なく相続財産の総額を減らすことが可能になります。
ただし、相続人に対して生前贈与をした場合、原則として、相続開始前3年以内に贈与されたものについては基礎控除額110万円以下の贈与財産についても課税対象の相続財産に加算されますので、注意が必要です。
贈与税の基礎控除を利用した相続税対策は、長期間行うことによって効果を発揮する手段ですので、元気なうちから早めに進めていくことが重要です。 -
(3)遺言書の作成
相続人同士の争いを防止するためには、遺言書の作成も有効な手段です。
被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合には、共同相続人による遺産分割協議によって遺産を分けることになります。しかし、遺産分割協議では、各相続人の利害が対立する結果、話し合いが長期化しトラブルになることも少なくありません。
有効な遺言がある場合でも、相続人による遺産分割協議により、遺言とは別の遺産分割ができるかどうかを協議することは可能ですが、話し合いが成立しなかった場合には有効な遺言書の内容に従って遺産を分けることになりますので、遺言書を作成しておくことによって、被相続人の希望どおりの遺産分割を実現することが可能です。また、有効な遺言書の存在により、遺産分割協議が不要になることも多く、相続人同士のトラブル回避も期待できます。 -
(4)トラブルが想定される財産を現金化
相続財産に土地や建物、有価証券といった財産が含まれている場合には、あらかじめ売却処分して、現金化しておくことも相続対策としては有効です。
不動産や有価証券などの財産は、物理的に分割することが困難であるため、遺産分割の場面において誰が取得するのかという点で争いになることがあります。このような場合には、あらかじめ現金化しておくことによって、法定相続分に応じて現金を分配するだけで済みますので、スムーズに遺産分割を行うことが可能になるでしょう。
また、相続税の支払いは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内における、現金一括納付が原則となります。相続財産の大部分が不動産という場合には、納税資金の負担という問題が生じますが、不動産を現金化することによって、相続人が納税資金を確保することも可能です。
4、相続対策を弁護士に相談するメリット
生命保険金の活用を含め、相続対策をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
-
(1)最適な相続対策を提案してもらえる
生前の相続対策としては、生命保険金、遺言書の作成、生前贈与などさまざまな方法が存在しています。どのような方法が最適な方法であるかは、遺産の総額・種類、法定相続人の数、想定される争いの内容、本人の希望などによって異なってきますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
どのような方針で進めるかを検討する際には、相続税や贈与税といった税金面への配慮も必要となります。相続税の負担を減らすことができたとしても、それを上回る贈与税の負担が生じてしまっては本末転倒ですので、税金面の対策も可能な弁護士や法律事務所に相談することをおすすめします。 -
(2)有効な遺言書の作成をサポート
相続対策としてよく利用される遺言書ですが、法律上、有効な遺言書を残しておく必要があります。遺言書の有効性に疑義が生じた場合には、せっかく相続人同士の争いを防止するために作成したにもかかわらず、逆に相続人同士の争いを招いてしまう事態になりかねません。
遺言書の形式としては、相続人が自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成される公正証書遺言がありますが、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が関与して作成するものですので、形式面による不備で遺言が無効になる可能性は低くなります。また、公正証書遺言は公証役場において20年間を超えて保管をしてくれますので、紛失や偽造といったリスクも少なくなります。さらに、公正証書遺言であれば、内容面についての遺言無効を争われるリスクも減少するでしょう。
他方で、自筆証書遺言の場合には、保管方法を誰かに伝えておかないと、紛失してしまうおそれがありますので、保管方法については注意が必要です。また、内容面において公正証書遺言よりも有効性を争われる可能性は高くなってしまいます。
ご本人が希望する内容の遺言書を作成することができるように、資料の収集から遺言書案の作成まで弁護士がサポートいたします。
60分無料
5、まとめ
相続対策を考える場合には、相続人に保障されている遺留分についても配慮する必要があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書も法律上は有効ですが、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求権を行使されるリスクがあることには注意しましょう。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士や司法書士なども在籍しており、生前の相続対策について、士業同士連携しながらサポートすることが可能です。相続対策をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺産相続専門チームの各士業が最適解を出せるよう、誠心誠意、取り組んでまいります。

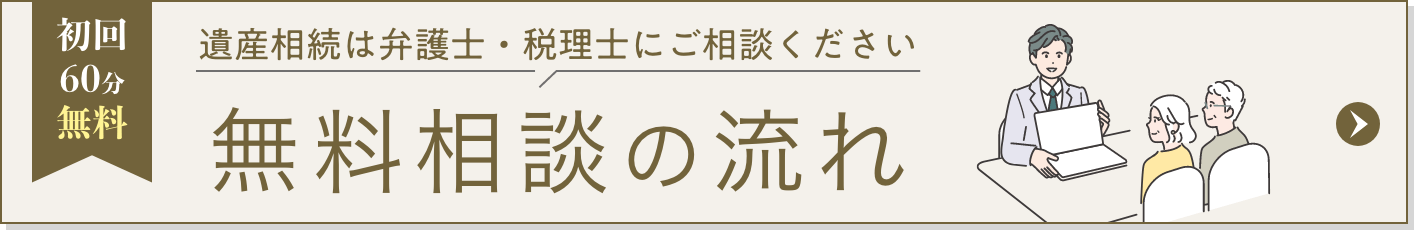
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を残す方)
-
2025年07月09日
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約

将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。
財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。
一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。
本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
2022年11月28日
- 遺産を残す方
- 遺産相続
- 遺留分
- 生命保険
- 相続対策

遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。「特定の相続人に多くの財産を渡したい」「相続人同士揉めないようにしたい」とお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
2022年09月20日
- 遺産を残す方
- 婚外子
- 非嫡出子
- 相続

さまざまな事情から、婚姻関係にない(結婚していない)相手との間で子どもが生まれることがあるでしょう。
婚姻関係にない男女間に生まれた子どもは「婚外子(非嫡出子)」として扱われることになるため、「認知」という手続きを行わないままでいると、婚外子の父親が亡くなったときに遺産を相続させられない可能性があります。
婚外子に対しても父親の遺産を相続させたい場合には、生前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
本コラムでは、婚外子の遺産相続における割合の考え方や相続税の計算方法、相続争いを避けるための対策方法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を残す方
- 遺留分対策に生命保険金は活用できる!? 例外ケースと相続対策

















