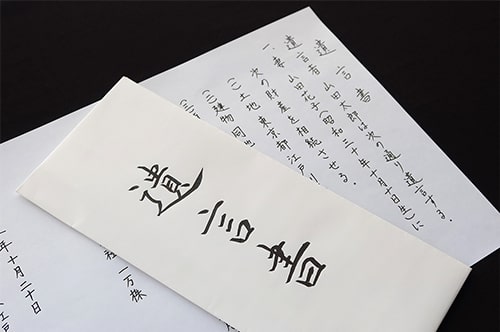- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割協議
- 弟の寄与分に対して兄が遺留分を主張! どのように解決していく?
遺産相続コラム
弟の寄与分に対して兄が遺留分を主張! どのように解決していく?
- 遺産分割協議
- 寄与分
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求

生前に親と同居し、介護など身の回りの世話をしていた場合、親の相続にあたっては、そのことを評価してほしいと考える方もいると思います。民法では、「寄与分」という規定があり、一定の場合には、遺産分割にあたって考慮される場合があります。
しかし、寄与分が認められた場合には、他の相続人よりも多く遺産をもらうことになりますので、他の相続人との間で遺産分割方法を巡って争いになることも珍しくありません。
本コラムでは、寄与分についての説明をはじめ、他の相続人から遺留分を主張された場合に寄与分がどのように扱われるかということについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、寄与分が認められる事例や寄与分権利者とは?
寄与分とはどのような場合に認められるのでしょうか?以下では、寄与分に関する基礎知識について説明します。
-
(1)寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人がいる場合に、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認めて、相続人同士の実質的公平を図ろうとする制度です(民法904条の2第1項)。
たとえば、母親はすでに亡くなり、二男が、要介護状態にある父親と長年同居して介護をしていたところ、その父親が死亡したとします。
法定相続人が長男と二男のふたりである場合に、もし、長男と二男に法定相続分どおり2分の1ずつの割合で遺産の分割をすると、二男が父親の介護をしなかった長男に対して不公平感を抱くことは、もっともといえます。
このような場合に、父親の遺産から二男に多く分配することで、長男と二男の不公平を解消するのが寄与分の制度です。 -
(2)寄与分が認められる者
寄与分が認められる者は、原則として共同相続人に限られます。
共同相続人以外の方が寄与をしたとしても、原則、その方に寄与分が認められることはありませんが、共同相続人の履行補助者と認められる立場にあった場合には、その方の行為は、当該共同相続人の寄与分として評価されることがあります。
また、令和元年7月に施行された改正相続法によって、相続人以外の方であっても、被相続人の親族で、被相続人に無償で療養看護その他の労務の提供をし、被相続人の財産が維持または増加した場合には、特別寄与料を請求することができるようになりました(民法1050条1項)。これによって、妻が夫の親の介護をしていたような場合でも、その親の死亡後に、妻自身が遺産から一定の財産を取得できるようになりました。 -
(3)寄与分が認められる事例
寄与分が認められるためには、当該相続人の行為が、
- ① 特別の寄与と評価できること
- ② 被相続人の財産の維持または増加があること
- ③ 寄与が無償であること
- ④ ①と②との間に因果関係があること
が必要になります。
このような要件を踏まえて、寄与分が認められる具体的な事例として、民法は以下のような場合を挙げています(民法904条の2第1項)。
① 被相続人の事業従事型
被相続人の事業従事型とは、被相続人が農業を営んできた場合や個人事業としてお店を経営していたような場合に、その手伝いをして労務を提供してきたようなケースです。
被相続人の事業従事型において寄与分が認められるためには、通常であれば他に人を雇って行うようなことを、長期間にわたって無償で手伝っていたということが必要でしょう。
たとえば、店の簡単な帳簿付け、店番、電話番程度の行為や、在学中に短期間お店の手伝いをしていた程度では特別の寄与までは認められないことになります。
② 財産給付型
財産給付型とは、被相続人が営む事業に対し、開業資金や運転資金などの金銭的な援助をしたようなケースを意味します。被相続人の経営する会社への援助や出資は含まれません。
寄与分が認められるかは、提供した財産の額や趣旨、内容などが考慮されますが、子どもが親に対し送金する小遣い程度では、特別の寄与までは認められないでしょう。
また、金銭的な援助の効果が相続開始時までに残っていることが必要です。
③ 療養看護型
療養看護型とは、親が病気などで介護が必要になった場合に、自宅で介護したような場合が典型的なケースです。
相続人自身が介護をする場合だけでなく、ヘルパーを利用していてもその費用を相続人が負担していた場合には、療養看護型として寄与分が認められる場合があります。
被相続人が要介護度2以上の状態にあることが、一つの目安と言われています。
④ その他の方法
その他の方法には、相続人が被相続人に対し扶養をした場合や、被相続人の住居資金を負担するなど被相続人の事業に関係のない財産上の給付をした場合、被相続人の財産の維持管理のための費用負担や労務の提供をした場合などが含まれます。
もっとも、夫婦であれば協力扶助義務があり(民法752条)、また、親族であれば扶養義務があり(民法877条)、このような義務を通常の範囲で履行したにすぎないような場合には、「特別の」寄与とは認められないでしょう。他方で、何人かいる兄弟のうちの一人だけが長年にわたって親に生活費の援助をしていたような場合には、特別の寄与として評価される場合があるでしょう。
60分無料
2、遺留分とは? 法定相続分とはどう違う?
遺留分とは、どのような権利をいうのでしょうか。以下では、遺留分についての説明と法定相続分との違いについて説明します。
-
(1)遺留分とは? 誰が遺留分権利者となるか?
被相続人には、生前同様に、遺言によって死後についても自分の財産を自由に処分することができます。しかし、他方で、民法は相続人の生活の保障などを目的として、遺言による財産処分の自由を一部制限しています。
遺留分とは、まさに、法律上、遺言による財産処分の自由を一部制限して、一定範囲の相続人に対して、遺産を取得することを保障する制度をいいます(民法1042条)。
被相続人が、相続人の一人にすべての遺産を相続させる旨の遺言書を残していたとしても、法律上保障されている遺留分については侵害することはできず、他の相続人は、受遺者や受贈者に対して、その遺留分が侵害されている限度で金銭を請求することができます(民法1046条1項)。これを「遺留分侵害額請求権」(かつては「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。)といいます。なお、遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者、子(代襲者・再代襲者を含む)及び直系尊属に認められています(民法1042条1項)。 -
(2)遺留分の割合
遺留分としてどの程度の相続割合が保障されているかは、相続人が誰であるかによって、異なります。具体的には、以下の割合に計算されます。
- 父母などの直系尊属のみが相続人である場合…法定相続分×3分の1
- それ以外の場合…法定相続分×2分の1
たとえば、父が死亡し、相続人として長男、二男がいる場合において、父が遺言で二男にすべての遺産を相続させる旨の遺言をしていたとします。この場合には、長男は遺産を一切相続できないことになってしまい、長男の遺留分が侵害されることとなります。
この場合は、上の「それ以外の場合」に該当しますので、長男の遺留分は、長男の法定相続分率である2分の1に2分の1を掛けて、長男の遺留分率4分の1が得られることになります。したがって、長男は、二男に対して、遺産の4分の1に相当する金銭の支払を、遺留分侵害額請求として求めることができます。 -
(3)遺留分と法定相続分の違いとは?
遺留分と似たような概念として法定相続分というものがあります。どちらも遺産額に対する割合を意味しているため、混同することもあるかもしれません。
法定相続分とは、大まかにいえば、被相続人が遺言によって相続分を指定しない場合に、法律が代わって定める各相続人の遺産の取り分のことをいいます。遺言がない場合には、共同相続人間で、各人の法定相続分を基礎として、それに修正を加える協議を行って、遺産分割するのが一般的です。
法定相続分は、遺産分割にあたって常に考える必要がありますが、遺留分は、主に特定の受遺者や受贈者に大きく偏った遺産の分け方をする内容の遺言があった場合に問題となります。なお、法定相続分は、遺留分と異なり、兄弟姉妹にも認められています(民法900条3号)。
3、寄与分と遺留分の関係
寄与分は、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができないとされています(民法904条の2第3項)。これは、寄与分よりも遺贈を優先させる趣旨であると読むことができます。
ところで、民法は、この規定の他に寄与分を制限すべき規定は置いていません。そのため、理論上は、他の相続人の遺留分を侵害するような寄与分を定めることも可能であるといえます。その意味では、寄与分が遺留分より優先するといえます。
4、遺留分と寄与分、法的にはどちらが優先されるの?
では、寄与分のある相続人に対して、遺留分侵害額請求がなされた以下のようなケースではどう考えればいいのでしょうか。
-
(1)寄与分のある共同相続人への遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈または贈与に限られており、寄与分については遺留分侵害額請求の対象とはされていません(民法1043条1項)。また、寄与分は、遺留分侵害額の負担の対象にもなっていません(同1047条)。
したがって、相続人のなかに家庭裁判所によって寄与分が認定された方がいて、その寄与分によって他の相続人の遺留分が侵害されているとしても、遺留分侵害額請求をすることはできないことになります。 -
(2)遺留分侵害額請求に対する寄与分の主張
では、相続人のなかに、被相続人の遺言によって多くの遺産を相続した方がいて、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合に、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた相続人は、寄与分を主張して遺留分侵害額請求を排除することはできるのでしょうか。
結論からいうと、寄与分を主張して遺留分侵害額請求を排除することは困難といえます。
なぜなら、上記のように、遺留分の計算において遺留分の計算の基礎から寄与分を控除することが民法に定められていないからです。また、遺留分侵害額請求が訴訟になった場合には地方裁判所の管轄事件となるのに対し、寄与分は、家庭裁判所の調停又は審判によって認定されるため、地方裁判所で争われる遺留分侵害額請求訴訟に対し、寄与分を主張することが手続き上困難であることがあげられます。参考:遺留分侵害額請求とは
60分無料
5、遺留分侵害額請求を受けた時あるいは寄与分の主張をされる時の対応と解決までの流れ
相続人の一人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、以下のような流れで進みます。このような請求を受けた場合には、以下のような対応をするとよいでしょう。
-
(1)遺留分侵害額請求をされた後の流れ
遺言などによって、自分の遺留分を侵害されたことを知った相続人は、財産を受け取った相続人に対し、遺留分侵害額請求をしてきます。遺留分侵害額請求権には、時効があるため、請求した事実を残すためにも、内容証明郵便で請求されることが通常です。
その後、遺留分侵害額としていくら支払うかについて話し合いをすることになります。
しかし、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停手続きで解決することになります(調停前置、家事法257条1項)。そして、調停でも解決することができない場合には、訴額に応じて、地方裁判所又は簡易裁判所(民訴5条14号)の訴訟手続きで解決が図られます。 -
(2)寄与分を主張するためには証拠が重要
寄与分が認められた場合には、寄与分を主張する相続人に多くの遺産が分配されることになりますので、それ以外の相続人は不満に思う場合が少なくありません。寄与分は、まずは話し合いで決めることになりますが、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停及び審判を求めることもできます(民法907条2項、家事法244条・274条1項)。
そして、寄与分を認めてもらうには、寄与分を主張する相続人が寄与分の要件を満たすことを証拠により立証することが重要になります。証拠がなければ、どれだけ寄与分があると主張しても家庭裁判所に認めてもらうことは困難です。
たとえば、療養看護型では、以下のようなものが証拠として考えられます。- 介護日誌などの記録(介護をした日付や内容のわかるもの)
- レシートや領収書(薬代やおむつ代、タクシー代など)
- 手紙・メールなどの記録
-
(3)遺留分侵害額請求をされた場合や寄与分の主張をされる場合には弁護士に相談を
遺留分侵害額請求をされた場合や寄与分の主張をお考えの場合には、遺留分侵害額の算定や寄与分の評価など、さまざまな法律上の争点が存在します。
相手から請求された遺留分侵害額が適切な金額なのかどうかや、寄与分を立証するためにどのような証拠が必要なのかについては、法律の専門家でなければ正確に判断することが難しい事項です。
弁護士であれば、交渉から調停、審判、訴訟まで、各手続きを一任することができますので、遺留分侵害額請求をされた場合や寄与分を主張されたい場合には、早期に弁護士に相談するようにしましょう。
60分無料
6、まとめ
被相続人が生前面倒をみてくれた相続人に対して、多く遺産を渡したいと思うのは当然の心情です。民法では、遺言という制度を定めて、そのような被相続人の遺思を尊重することができるようになっています。しかし、それによって他の相続人の遺留分を侵害することになれば、争いが生じることも少なくありません。
全国展開するベリーベスト法律事務所では、税理士や司法書士とも連携可能ですので、遺産相続に関する相談から、登記や相続税のことまで一度で解決することが可能です。
遺産相続でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産分割協議)
-
2025年03月19日
- 遺産分割協議
- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年01月29日
- 遺産分割協議
- 相続争い
- 絶縁

親が亡くなり相続が発生すると、子どもは親の相続人として相続手続きをしなければなりません。しかし、さまざまな理由から子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁状態にあるという方もいるかもしれません。
そのような場合、遺産相続において相続争いが発生することも多く、通常の相続手続きとは異なる特別な手続きが必要になる可能性もあります。ご自身での対応が難しいときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
今回は、親の遺産相続にあたり、絶縁している兄弟姉妹の間で相続争いが生じた場合の対処法と注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2024年11月06日
- 遺産分割協議
- 遺言無効確認訴訟
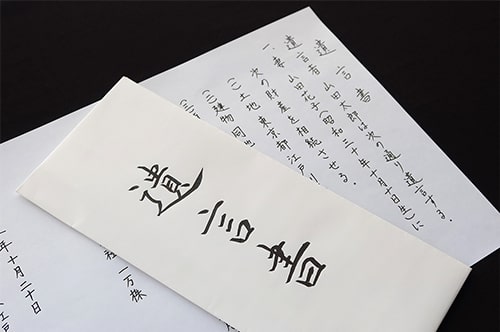
遺言無効確認訴訟とは、被相続人(亡くなった方)による遺言が無効であることについて、裁判所に確認を求める訴訟です。
遺言書の内容に納得できず、遺言書が作成された経緯に不適切な点や疑問点がある場合には、遺言無効確認訴訟の提起を検討しましょう。
本記事では遺言無効確認訴訟について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が詳しく解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割協議
- 弟の寄与分に対して兄が遺留分を主張! どのように解決していく?