- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる? 弁護士が解説
遺産相続コラム
特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる? 弁護士が解説
- 遺留分侵害額請求
- 特別受益
- 遺留分
- 遺留分侵害額請求

自分の所有する財産をどのように処分するかは個人の自由です。特定の子どもにだけ財産を贈与するということも当然認められた行為です。
しかし、遺産相続の手続きなどが始まる前に、被相続人(亡くなった方)が多額の資産を特定の子どもにだけ贈与していた場合、他の相続人からすると不平等に思うことがあるでしょう。そのため、民法では一定の条件を満たす贈与について、「特別受益」として被相続人の相続財産に組み込むことにしています。
今回は、特別受益の概要を解説するとともに、遺留分侵害額請求の対象になる贈与や持ち戻しの免除をした場合の効果、特別受益の持ち戻しの計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
1、特別受益の基礎
遺産相続にはさまざまな用語があるため、混乱する方は少なくありません。最初に、本コラムのテーマである特別受益について、どういうものなのかを説明します。
-
(1)特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特定の生前贈与や遺贈などの利益のことです。
- 生前贈与 被相続人が存命中に財産を受け渡すこと。
- 遺贈 被相続人の死後、被相続人の遺言によって財産を受け渡すこと。
それぞれ、被相続人が特定の相続人に無償で財産を継承させることから、相続人間で不公平を抱きやすいものといえるでしょう。
特別受益については、民法903条に「特別受益者の相続分」の規定があります。
同条により、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した相続財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」とされます。
つまり、相続人間の公平のため、被相続人が亡くなり相続が開始した時点の相続財産に特別受益分を加え、そのうえで各相続人への具体的な相続分を考えることを目的に定められた考え方です。 -
(2)特別受益者になれる人
特別受益者とは、被相続人からの特別受益を受けていた方のことを意味します。相続人以外の第三者に贈与がなされても、原則として、それは特別受益にはなりません。つまり、特別受益者となるのは、相続人に限られます。
たとえば、被相続人Aには配偶者Bと子どもC、さらに孫であるDがいるとしましょう。このケースでは、被相続人Aの相続人となる対象は、配偶者Bと子どもCです。
被相続人Aが、相続人ではない孫Dに対して贈与を行うような場合は、特別受益に含まないのが原則になります。ただし、孫Dへの贈与が形式だけで、実質的には被相続人の子どもC(孫の親であり相続人)に贈与しているような場合には、子どもCの特別受益にあたると解される余地があるため、注意が必要です。 -
(3)特別受益の対象となる贈与
特別受益は、被相続人から受けた贈与のすべてが該当するわけではありません。特別受益の対象となる贈与は、以下のものに限られています。
- 遺贈
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
たとえば、結婚する際に親から持参金をもらった場合や住宅購入のために資金援助を受けた場合は「婚姻のための贈与」に該当し、事業を始めるための開業資金の援助を受けた場合などについては「生計の資本としての贈与」に該当するとみなされ、特別受益の対象となる贈与に含まれます。
2、特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる?
特別受益で継承された被相続人の財産は、遺留分侵害額請求の対象になるのでしょうか。ここからは、遺留分の概要や遺留分侵害額請求について解説します。
-
(1)遺留分の考え方
遺留分とは、法律上、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障された一定割合の持分のことです。
通常、これから相続人になるはずの方(推定相続人)は遺産に対する期待があるため、それを保護する必要性から、遺留分という権利が認められています。
遺留分が認められる割合は、直系尊属(自分から見たときに、父母・祖父母など血のつながりがある上の世代)のみが相続人になる場合、相続財産の3分の1、その他の場合には相続財産の2分の1です。法定相続分が2分の1の場合には、法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1で、相続財産の4分の1が遺留分ということになります。
お使いの機種によって横にスクロールが可能です。遺留分の割合について
相続人の構成 ①相続人全員の
遺留分割合②相続人それぞれの遺留分割合 配偶者 子ども 父母 兄弟 配偶者のみ 1/2 1/2 × × × 配偶者と子ども 1/2 1/4 1/4 × × 配偶者と父母 1/2 1/3 × 1/6 × 配偶者と兄弟 1/2 1/2 × × × 子どものみ 1/2 × 1/2 × × 父母のみ 1/3 × × 1/3 × 兄弟のみ × × × × × ここからは、遺留分を算定するための財産が5000万円で、相続人が配偶者と子ども一人というケースを例に、具体的な数字で見ていきましょう。
このとき、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1、遺留分割合は配偶者と子どもになるので2分の1です。遺留分は配偶者と子どもでそれぞれ4分の1となり、計算式は以下のようになります。5000万円(被相続人の財産)×4分の1(遺留分)=1250万円(遺留分として有する金額)
つまり、被相続人の財産に対して、配偶者と子どもは1250万円ずつの遺留分を有することになるのです。
この遺留分を守るために、遺留分を侵害する額(上のケースでは1250万以下の額)については、遺贈または贈与を受けた者に侵害額を請求することができるとされています。
かつては、遺留分を確保するためには、遺留分減殺請求という制度が定められており、遺留分減殺請求権を行使すると、当然に物権的効果が生じ、遺贈または贈与された財産のすべてが、遺留分権利者(遺留分の権利を有する方)と受遺者または贈与者との共有になるとされていました。
しかし、平成30年の民法改正で、遺留分減殺請求ではなく、遺留分を侵害した額を請求できるようになり、遺留分権利者の権利が守られることになったのです。
これは、遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分権利者が「遺留分を侵害する額に相当する金額を請求することができる」という制度であり、遺留分の侵害に対しては金銭的に解決することになりました。参考:遺留分についての基礎知識
-
(2)遺留分侵害額請求の対象になる贈与
特別受益であっても、遺贈や贈与であることに変わりはありません。そのため、原則として相続発生前10年以内に行われたものであれば、遺留分侵害額請求の対象となります。
そして、遺留分が侵害されているかどうかを判断するためには、まず遺留分がいくらなのか算定しなければなりませんが、民法第1043条では、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定されています。
つまり、遺留分を算定するための財産の価額には、相続時の財産の他に被相続人が贈与した財産も含まれるということです。
当然そこには、特別受益に該当する贈与も含まれますが、期間の制限があり、相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与の価額と、相続開始前1年間になされた相続人以外の者に対する贈与の価額は、すべて遺留分を算定するための財産に算入されます。
また、それより前になされた贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与の価額については、遺留分を算定するための財産に算入されることとなります(民法第1044条)。
したがって、相続人の中に被相続人から特別受益を受けている者がいる場合には、遺贈または相続開始後10年以内の贈与であれば、原則として、その額は遺留分を算定するための財産の価額に加えることが可能です。また、算定の結果、その特別受益が遺留分を侵害しているようであれば、特別受益となる贈与または遺贈に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
60分無料
3、持ち戻しの免除と遺留分の関係性
特別受益は「持ち戻し」をすることがあります。持ち戻しの意味や、持ち戻しの免除があった際の遺留分侵害額請求について、解説します。
-
(1)持ち戻しとは
原則、遺産分割は法定相続分にしたがって遺産分けを行います。しかし、特別受益を受けた相続人がいると、法定相続分どおりの分配は不公平だと感じる方もいるでしょう。
そこで、特別受益の対象となる贈与を受けたケースでは、遺産の前渡しがあったと評価をし、遺産分割においては特別受益を相続財産に含めて計算することが認められています。これを特別受益の「持ち戻し」といいます。
なお、特別受益は、相続人同士の公平を図る制度であるため、法定相続人以外の人が贈与による利益を得ていても、持ち戻しの対象外です。 -
(2)持ち戻しの免除とは
持ち戻しの免除とは、被相続人の意思で、特別受益を相続財産に持ち戻さずに、生前贈与や遺贈を考慮することなく分配を行わせることです(民法第903条第3項)。なお、被相続人は免除の意思を表示した後でも、自由にこれを撤回できます。
特別受益となるような贈与であったとしても、遺産は被相続人の所有財産であることから、被相続人が自由に処分できるのが原則であり、持ち戻しを行わないとする意思を有する際は、その意思を尊重すべきと考えられるからです。
このように、特別受益は持ち戻しされるのが原則である一方、持ち戻し免除の意思表示があれば、例外的に持ち戻しが免除されます。
長年連れ添った夫婦については、持ち戻しの免除の意思があるのが通常のため、平成30年の民法の改正によって「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与」については、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定するとされました(民法第903条第4項)。
持ち戻しの意思表示方法に法律上定めはありませんが、最終的に争いになれば証拠が必要になるため、遺言に記載するなど、書面で残しておくことが望ましいといえます。
書面の記載内容は、「遺言者は、令和○年○月○日、○○に対し金500万円を贈与したが、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定にあたっては、当該贈与額は、相続財産の価額に加えないものとする」といった形にしましょう。 -
(3)持ち戻し免除があっても遺留分侵害額請求の対象になるのか
持ち戻しの免除は被相続人の意思を尊重するものですが、前述の通り、相続人には遺留分という最低限の権利が認められています。
持ち戻しの免除によってこの権利まで制限できるとしたら、遺留分制度の意味がなくなってしまうでしょう。最高裁判所は、平成24年1月26日の判決で持ち戻し免除の意思表示は、遺留分を害しない範囲においてしか効力を有しないと判断しました。持ち戻し免除があっても特別受益について遺留分侵害額請求の対象になるとされています。
4、特別受益の持ち戻しによる計算方法と具体例
ここからは、特別受益の持ち戻しによる計算方法について説明します。
-
(1)基本的な特別受益の持ち戻しの計算式
特別受益を受けた相続人がいるときは、特別受益の持ち戻しにより、相続財産に特別受益の金額を加えたものを「みなし相続財産」として、遺産分割を行います。
相続開始時の財産+特別受益とされる贈与額=みなし相続財産
特別受益者ではない相続人は、みなし相続財産に法定相続分を掛けて、相続分を計算します。これに対して、特別受益者である相続人は、みなし相続財産に法定相続分を掛けた後、特別受益の額を引くことで計算を行います。
特別受益者ではない相続人 (相続財産+贈与額)×法定相続分 特別受益者である相続人 (相続財産+贈与額)×法定相続分-特別受益の財産額
なお上記は、特別受益が遺留分を侵害していないケースの計算方法になります。遺留分の侵害がある場合には、計算がもう少し複雑になるため、注意が必要です。
-
(2)特別受益の持ち戻しの計算事例
ここからは、2つのケースに分けて計算事例を紹介します。
【設例】- 相続財産が3000万円
- 法定相続人は長男A、長女B、次女Cの3人
- 被相続人は、長男Aに対して2000万円の住宅資金援助を行い、長女Bに対して1600万円の結婚資金の贈与を行い、いずれの贈与も特別受益にあたるものとする
この事例において、持ち戻しの免除があった場合となかった場合とで、各相続人の具体的相続分がいくらになるのかを比較してみましょう。
① 持ち戻し免除なしのケース
被相続人による持ち戻し免除の意思表示がなければ、相続人に対する特別受益については、相続財産に加えてみなし相続財産を計算することになります。
この場合のみなし相続財産は、3000万円+(2000万円+1600万円)=6600万円です。
そして、各相続人の具体的相続分は、以下のようになります。- 長男A:6600万円×1/3-2000万円=200万円
- 長女B:6600万円×1/3-1600万円=600万円
- 次女C:6600万円×1/3=2200万円
② 持ち戻し免除ありのケース
持ち戻しの免除の意思表示があるケースでは、特別受益の持ち戻しを考慮せずに遺産分割を行います。
そのため、各相続人の具体的相続分は、以下のようになります。- 長男A:3000万円×1/3=1000万円
- 長女B:3000万円×1/3=1000万円
- 次女C:3000万円×1/3=1000万円
ただし、法律上遺留分が保障されていることから、持ち戻しの免除の意思表示があっても、贈与財産の価額は遺留分算定基礎となる財産に算入されます。
上記のケースは、次女Cの遺留分(1100万円=2200万円×1/2)侵害により、Cは遺留分侵害額請求が可能です。
5、遺留分侵害額請求を受けた場合の流れと認められないケース
遺留分侵害額請求を受けたときは、どのように対応すればよいのでしょうか。
-
(1)遺留分侵害額請求を受けたときの流れ
遺留分侵害額請求を受けた際には、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
① 内容証明郵便が届く
遺留分侵害額請求の方法には、法律上の特別な定めはありませんが、後日の証拠とするために、配達証明付きの内容証明郵便を利用して行われるのが一般的です。
そのため、まずは遺留分権利者から内容証明郵便による遺留分侵害額請求を受けることになるでしょう。
② 話し合いをする
遺留分侵害額請求を受けたときは、遺留分権利者との話し合いによって、その後の対応を決めていきます。遺留分の侵害が事実であれば、遺留分権利者の請求に応じなければなりません。
遺留分権利者が遺留分の計算を間違えていることもありますので、自分でもしっかりと計算して対応することが大切です。
③ 調停
話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申し立てをすることになります。遺留分の争いは調停前置主義がとられているため、いきなり裁判を起こすことはできません。必ず調停手続きを経ている必要があります。
④ 裁判
調停でも解決できない場合には、最終的に民事裁判を起こして解決を図ります。裁判は、非常に複雑かつ専門的な手続きになりますので、弁護士のサポートを受けながら進めていくようにしましょう。 -
(2)遺留分侵害額請求が認められないケース
遺留分の侵害があった場合には、相手に対して遺留分侵害額請求をすることができるのが原則です。しかし、以下のような2つのケースでは、例外的に遺留分侵害額請求が認められないことがあります。
① 時効
遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始のときから10年という期限があります。
この期限を経過してしまうと、時効によって遺留分侵害額請求をすることができなくなってしまうため、注意してください。
② 生前に被相続人が遺留分権利者に生計の資本として多額の贈与をしていた場合
遺留分侵害額を計算する際には、遺留分額から特別受益財産額を控除します。遺留分権利者が多額の贈与を受けていたようなケースでは、遺留分権利者が請求できる遺留分額がゼロになることもあります。
この場合には、遺留分の侵害がなく遺留分侵害額請求はできません。
60分無料
6、まとめ
本コラムでは、特別受益の概要や特別受益がある場合の遺留分侵害額請求などについて、解説してきました。
「子どもが争わないように」と生前贈与されることが多いのですが、結果的にそれが原因で相続時に争いに発展するケースがよくあります。相続争いが生じると、兄弟姉妹同士の仲が悪くなるなど、よいことはひとつもありません。
少しでももめそうなら、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベストグループには、弁護士の他に、税理士や司法書士も在籍し、幅広い相続問題を解決できる体制を整えております。相続問題でのお困りごとは、ぜひお気軽にご相談ください。

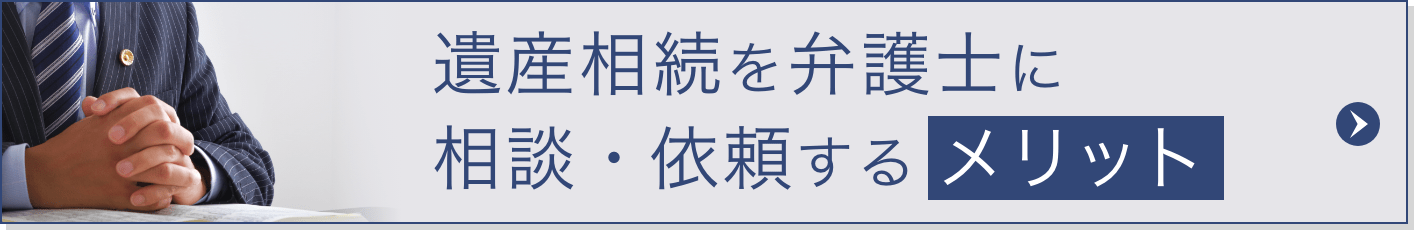
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)
-
2026年01月07日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年10月15日
- 遺留分侵害額請求
- 遺言書
- 全財産
- 無効

「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年07月23日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求
- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる? 弁護士が解説


















