- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割
- 遺産分割協議書を作成できる人は誰? 自分でも作成できる?
遺産相続コラム
遺産分割協議書を作成できる人は誰? 自分でも作成できる?
- 遺産分割
- 遺産分割協議書
- 作成できる人

遺産相続の手続きにおいて、「遺産分割協議書」は遺産の分け方を決める重要な書面です。遺言書があったとしても、作成を検討しなければならないケースも起こり得ます。
遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、自分で作成するのが難しい場合は、専門士業への依頼を検討したいところです。しかし、遺産分割協議書を作成できる人は誰なのか、よくわからない方もいらっしゃるでしょう。
遺産分割協議書を作成できる専門士業としては、行政書士・司法書士・税理士・弁護士が挙げられます。それぞれ対応できる業務の範囲に違いがあるので、ご自身の状況に合わせて依頼先を決めるとよいでしょう。
本コラムでは、遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)の種類や、各専門士業の業務範囲、ご自身で作成するメリット・デメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、遺産分割協議書を作成できる人は誰?
遺産分割協議書の作成については、まず、相続人が自分で作成するか、または専門士業に作成を依頼するかについて、検討することになります。
相続人の間で作成できる人がいない場合や、作成に不安がある場合には、専門士業に遺産分割協議書の作成を依頼するとよいでしょう。
-
(1)遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議書の作成が必要な理由は、主に以下の2つです。
① 相続人間のトラブルを防止するため
遺産分割の方法につき、相続人全員の合意内容を明確化して、後に相続人間のトラブルに発展するリスクを防ぐことができます。
② 遺産の名義変更手続きや相続税申告の際に必要なため
金融機関における相続に伴う手続き(預貯金口座の解約)、不動産の相続登記手続き、相続税申告などを行う際に、遺産分割協議書の提出が必要になります。 -
(2)遺産分割協議書の作成を依頼できる専門士業
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門士業は、以下の4つです。
- ① 行政書士
- ② 司法書士
- ③ 税理士
- ④ 弁護士
各専門士業にはそれぞれ業務範囲が設定されており、遺産分割協議書の作成に関して、各専門士業ができることには違いがある点に注意が必要です。具体的な業務範囲については、後述します。
2、遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット
遺産分割協議書は、相続人が自分で作成することもできます。相続人の中で、遺産分割協議書を作成できる人がいれば、専門士業に依頼せずに作成を試みてもよいでしょう。
ただし、遺産分割協議書を相続人が自分で作成することには、デメリットもあるので注意が必要です。
-
(1)遺産分割協議書に記載すべき内容
遺産分割協議書には、「誰が」「どの遺産を」「どのくらい」相続するのかを明確に記載する必要があります。
たとえば預貯金であれば、
「A銀行B支店の普通預金口座(口座番号:〇〇〇〇〇〇〇)にある預貯金のうち」
「1000万円分をXが、残りをYが相続する」
という内容を記載しておけば、「誰が」「どの遺産を」「どのくらい」相続するのかが明確にわかります。3つのポイントを明確に特定することを意識して、各遺産の分け方を記載しましょう。
また、遺産分割協議書では、すべての遺産について分け方を決めておくことが大切です。遺産の把握に漏れがあった場合、漏れていた部分について後から新たに遺産分割協議をしなくてはなりませんので、遺産の調査を慎重に行いましょう。
遺産分割協議書の内容が固まったら、内容によっては公正証書にすることも検討します。
遺産分割に関して相続人が何らかの義務を負う場合(代償分割の代償金支払いなど)、その相続人が債務を履行しないときにスムーズに強制執行を申し立てられる点が公正証書化のメリットです(民事執行法第22条第5号)。参考:遺産分割協議書の作成
-
(2)遺産分割協議書を自分で作成するメリット
遺産分割協議書を相続人が自分で作成するメリットは、専門士業への依頼費用がかからない点です。
専門士業に依頼すると、遺産分割協議書の作成だけでも、最低数万円程度の費用がかかります。相続人の中に遺産分割協議書を作成できる人がいれば、自分で作成することで、費用を節約できます。 -
(3)遺産分割協議書を自分で作成するデメリット
ただし、遺産分割協議書を相続人が自分で作成する場合、以下のデメリットがあります。
- 条文の表現が不明確になり、紛争を誘発したり、相続手続きの停滞を招いたりするおそれがある
- 法定相続人や遺産の把握漏れが生じ、後日遺産分割がやり直しや漏れた部分の遺産分割を別途行わなければならない可能性がある
トラブルなく相続手続きを終えたい場合には、たとえ相続人の中に作成できそうだという人がいるとしても、遺産分割協議書の作成は専門士業に依頼した方が賢明です。
60分無料
3、遺産分割協議書の作成につき、各専門士業ができること
前述のとおり、専門士業で遺産分割協議書を作成できる人は行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業です。各専門士業の間では、遺産分割協議書の作成に関する業務範囲が異なります。依頼前に知っておいた方がよいでしょう。
-
(1)行政書士
行政書士は、遺産分割協議書の作成を行うことができます(行政書士法第1条の2第1項)。ただし行政書士は、遺産分割に関する紛争解決を取り扱うことはできません(弁護士法第72条、行政書士法第1条の2第2項)。
そのため、遺産分割協議書の内容についてのアドバイスを、行政書士から受けることはできません。相続人間で話がまとまって、合意した内容を遺産分割協議書にしたいだけという場合には、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼することも検討できます。 -
(2)司法書士
司法書士は、登記業務に関連して、法務局・地方法務局に提出する書類の作成を行うことができます(司法書士法第3条第1項第2号)ので、不動産が関係する相続においては遺産分割協議書を作成することができます。ただし、この場合も遺産分割の内容に関するアドバイスをしたり、相続人の代理人として交渉をしたりすることはできません。
例外的に、不動産が関係しなくても、認定司法書士については、140万円を超えない範囲の争いがある場合は、仲介や交渉、アドバイスなどが可能です。ただし、この場合も相続資産が140万を超え、調整や交渉などが必要となるケースでは、遺産分割協議書の内容に関するアドバイスをすることはできませんので注意しましょう。
不動産の名義変更などを伴う相続で、トラブルなくスムーズに内容が決定して、かつ後日問題になりうる複雑な事項がないときに利用を検討することになるでしょう。 -
(3)税理士
税理士は、税務署に提出する書類の作成を行うことができます(税理士法第2条第1項第2号)。したがって、相続税申告に必要となる場合に限り、税理士による遺産分割協議書の作成が認められます。
これに対して、相続税申告を行わない場合(相続財産等の総額が基礎控除額以下の場合など)には、税理士が遺産分割協議書を作成することはできません。また、税理士も行政書士・司法書士と同様、遺産分割協議書の内容に関するアドバイスを行うことは許されません。
税理士に遺産分割協議書作成の依頼を検討するシーンは、相続税の申告などを依頼することが決定していて、親族間で争うことなくスムーズに遺産分割協議が終了し、後日トラブルになりうる複雑な事項がないとき、といえるでしょう。 -
(4)弁護士
弁護士は、遺産分割協議書の作成を全面的に行うことができます。
また、行政書士、司法書士、税理士とは異なり、弁護士は遺産分割に関する紛争解決の取り扱いも認められています。したがって、遺産分割協議の内容に関するアドバイスから、実際の遺産分割協議書の作成まで幅広く依頼できる点が、弁護士の大きな強みです。
詳細は次の章で述べますが、遺産の内容が複雑なとき、親族間で争いがあるときなどは、弁護士であれば、遺産分割協議書の作成だけでなく、状況の確認からアドバイスの提供、他の相続人との調整や交渉も可能です。
60分無料
4、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した方がよいケース
遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)はほかにもいる中で、特に弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼すべきケースとしては、以下の場合が挙げられます。
-
(1)遺産分割協議でもめている場合・もめそうな場合
遺産分割に関する紛争解決を取り扱えるのは、専門士業の中でも弁護士のみです。
すでに遺産分割協議で意見の対立が発生している場合や、相続人同士の関係性が悪く、今後もめ事に発展しそうな場合には、弁護士に交渉や調整の段階から遺産分割協議書の作成まで依頼することをおすすめします。 -
(2)遺産分割で話し合うべき内容・注意点がわからない場合
遺産分割協議書の内容についてアドバイスができるのは、専門士業の中でも弁護士のみです。
遺産の内容が複雑で遺産分割協議で何を話し合うべきかわからない場合や、遺産分割における注意点について専門的な助言を求めたい場合には、弁護士が依頼先として適任です。 -
(3)面倒な相続手続きを一括して任せたい場合
弁護士は、遺産分割協議書の作成のみならず、その後の銀行での相続手続きなども依頼できる場合があります。やるべきことがたくさんある中で、手間なくスムーズに相続手続きを完了したい場合には、弁護士に相続手続きを一括して依頼するのがおすすめです。
なお、司法書士や税理士と連携している弁護士に依頼すれば、相続登記や相続税申告の手続きについても、必要に応じて対応してもらうことが可能です。
60分無料
5、まとめ
専門士業で遺産分割協議書を作成できる人は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の4士業です。
その中でも弁護士は、業務範囲の制限なく遺産分割協議書を作成できるほか、その他の相続手続きについても全般的に対応することができます。そのため、遺産相続の手続きを一括して任せたい場合には、弁護士への依頼がおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関する法律相談を随時承っております。遺産分割協議書の作成についても、記載事項・記載方法や法律上の注意点などに関して、依頼者のご状況を踏まえたオーダーメードのアドバイスをご提供することが可能です。
相続手続きへの対応にお悩みの方や、遺産分割協議書を作成できる人を探している方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所へご相談ください。遺産相続専門チームの経験豊富な弁護士が、誠心誠意、サポートいたします。
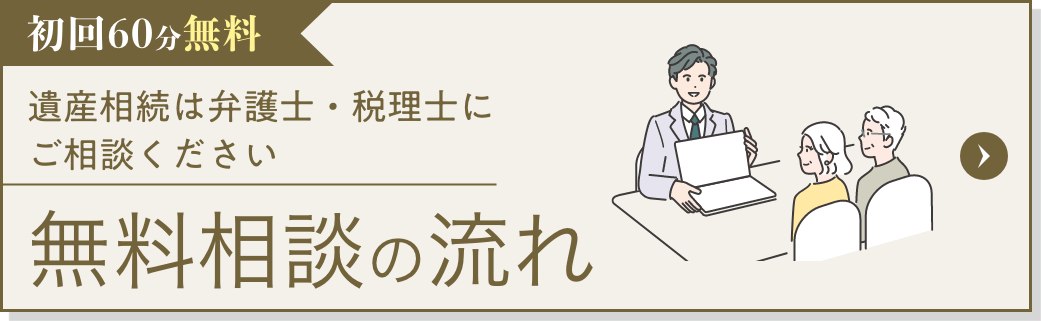
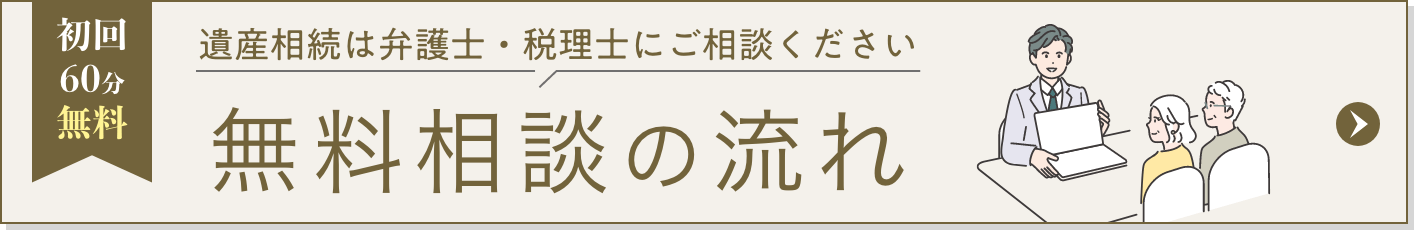
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産分割)
-
2025年12月15日
- 遺産分割
- 隠し子
- 相続

親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。
結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。
今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -
2025年09月11日
- 遺産分割
- 再転相続

法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。
再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。
今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年03月19日
- 遺産分割
- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割
- 遺産分割協議書を作成できる人は誰? 自分でも作成できる?


















