- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 相続で利益相反行為が問題になるケースとは? 対処法と注意点を解説
遺産相続コラム
相続で利益相反行為が問題になるケースとは? 対処法と注意点を解説
- 遺産を受け取る方
- 利益相反
- 相続
- 問題
- 注意点

遺産相続の手続きを進める際は、「利益相反」に気を付けましょう。
利益相反とは、当事者が複数人いる場合に、一方にとっては有利となり、他方にとっては不利益となることを言います。
利益相反行為を適切に対処しなければ、遺産分割協議や相続登記などもすべて白紙となり、最初からやり直さなければならない可能性があるため、注意が必要です。
本コラムでは、遺産相続で利益相反が問題となるケースや対処法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、利益相反行為とは? 遺産相続で利益相反が問題になり得るケース
まずは、遺産相続において利益相反が生じてしまう可能性があるケースについて、解説します。
-
(1)未成年者や成年被後見人が共同相続人の場合
未成年者や成年被後見人は、原則として単独で法律行為をすることができず、法律の規定により、次のように法定代理人が定められています。
- 未成年者の場合:親権者(または未成年後見人)
- 成年被後見人:家庭裁判所で選任された成年後見人
このような親権者・未成年後見人・成年後見人は、財産管理全般について代理権を行使することができます。また、このような法定代理人がいるケースで利益相反が問題となり得るのは、遺産分割と相続放棄の場面です。
【① 遺産分割】
相続人が複数人いる場合は、原則として遺産分割を行い、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で決めなければなりません。
遺産分割は、相続人全員が合意すれば自由に分割方法を決めることができますが、相続人とその相続人の法定代理人が共同相続人であれば、双方の間で利益が相反することになります。
たとえば、父が亡くなり、母(父の配偶者)と未成年の子どもが残された場合、法定相続人は母と子どもです。子どもが成人していれば、母と子どもで遺産分割協議を行います。しかし、子どもが未成年者であれば、親権者である母が法定代理人となり、母の思い通りに遺産分割ができてしまうことになります。
この場合、母と子どもは利益が相反する関係となるため、母は子どもを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
なお、利益相反全般に共通することですが、利益相反の有無は実際に生じた利益や不利益から判断するものではなく、行為を外形的にみて形式的・客観的に判断されます。親権者の主観や内心の事情は判断の要素になりません。
つまり、たとえ未成年者や成年被後見人に有利な遺産分割をしたとしても、遺産分割という行為自体が利益相反行為であることから、代理人として行動することはできません。
【② 相続放棄】
相続人となった場合、遺産を相続せず相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法 第939条)。
相続人全員が相続放棄をする場合、それによって利益を得る人がいないため、利益相反行為に該当することは基本的にはありません。しかし、法定代理人が未成年者や成年被後見人を代理して、未成年者や成年被後見人にのみ相続放棄をさせることは利益相反となるため、認められません。
たとえば、母と子どもがともに相続人になっているときに、母が子どもを代理して、子どもの相続放棄のみを行うことはできません。たとえ、その後、母自身も相続放棄するとしても、子どもだけの相続放棄をするということはできないのです。 -
(2)遺言執行者が存在する場合
被相続人(財産を残す方)は、遺言の中で、遺言の内容を実現させるために必要な行為(預貯金の解約や登記名義変更など)の権限を有する、「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には、相続人のほか第三者を指定することも可能です。
遺言執行者は、遺言によって定められた事項を実行していくものなので、通常は利益相反が問題になることはないですが、相続財産を売却するような場合は、利益相反が生じることもあります。
たとえば、「相続財産を売却して借金を清算した上で残った現金をAに相続させる」という遺言があった場合に、遺言執行者が相続財産を買い受けたとすると、民法が無権代理行為とみなしている自己契約となり、利益相反行為に該当します(民法第108条1項)。
60分無料
2、利益相反が問題となった場合の対処法|特別代理人
親権者や後見人が代理行為をできない場合は、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は、子どもや成年被後見人の代理として、家庭裁判所が定めた行為を代理するという限定的な権限を有します。
特別代理人の人選や資格については法律上特に規定はありませんが、一般的に相続について利害関係がない親族や、弁護士などの専門職から選任されることがほとんどです。
- 1. 必要書類の提出
- ・申立書
- ・戸籍謄本(全部事項証明書)
※未成年者のものと、親権者(または後見人)のものが必要です。 - ・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- ・特別代理人候補者の承諾書
- ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
- ・利害関係を裏付ける資料(利害関係人からの申し立ての場合のみ)
- 2. 家庭裁判所から照会書の送付・回答
- 3. 審理(書面の照会や審問など)
- 4. 審判
審判が下されると、審判所謄本が送られます。
特別代理人が選任された場合は、特別代理人であることを証明する書面となるため、大切に保管しましょう。

3、利益相反が問題となった場合の対処法|相続放棄
未成年者や成年被後見人に相続放棄をさせる場合は、共同相続人である親権者や後見人が代理して行うことはできません。
しかし、共同相続人である親権者や後見人自身が、相続放棄を選択することはできます。自身の相続を放棄することで、未成年者や成年被後見人の代理人として遺産分割を行うことが可能です。また、自身の相続放棄と同時に、子どもや成年被後見人の相続放棄を行うことも認められています。
ただし、共同相続人である法定代理人が相続放棄をしたとしても、未成年者の子どもなどが2人以上いる場合は利益相反の関係が解消されないため、注意が必要です。
なぜ、そのような事態になるのか、母と子ども2人(長男と次男)が法定相続人である場合を例に説明します。
母自身が相続を放棄することで、代理行為を行うことができるようになることは前述したとおりです。ただし、長男と次男、両方を代理して遺産分割を行うことはできません。なぜなら、長男の取り分を多くすれば、次男の取り分は減るということになり、子どもと子どもの間で利益が相反する関係になるためです。
このようなケースでは、長男の代理人が母で、次男のために特別代理人を選任するといった対応が必要です。
60分無料
4、特別代理人を選任せず遺産分割協議を進めたらどうなる?
利益相反行為であるにもかかわらず、法定代理人が代理権を行使した場合は、「無権代理行為」に該当します。追認されなければ、決めた事柄は無効として扱われます(民法第113条)。
追認とは、本来であれば取り消しに該当する行為ではあるものの、有効な法律行為であるとして認めることを指します。
たとえば、親が無権代理行為をした場合、成人に達した子どもが追認をしなければ法律効果は子どもに帰属しないことになるため、遺産分割協議や相続登記などもすべて白紙となり、ゼロからやり直さなければなりません。
未成年者が成年に達してから追認することや、家庭裁判所から選任された特別代理人が従前行われた遺産分割協議を追認することはできると考えられますが、追認されるまで相続財産は宙に浮いた状態となります。
5、まとめ
未成年者や成年被後見人が相続人に含まれる場合は、特別代理人の選任が必要となるケースがほとんどです。
特別代理人は家庭裁判所が定める事項を実行するほか、その相当性を担保するという重要な役割を担います。特別代理人を頼める適任者がいない場合は、弁護士に依頼することをご検討ください。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士も在籍しているため、遺産分割協議や相続税などのご相談について、必要に応じて各士業が連携を取りながらサポートすることができます。相続手続きや利益相反などでお困りの際は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
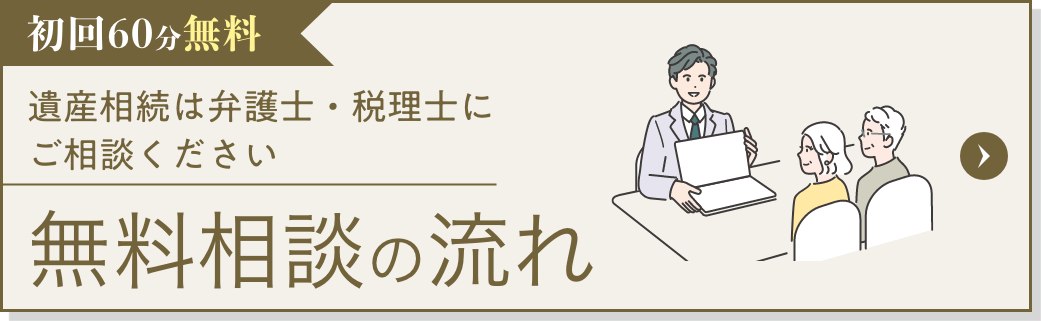
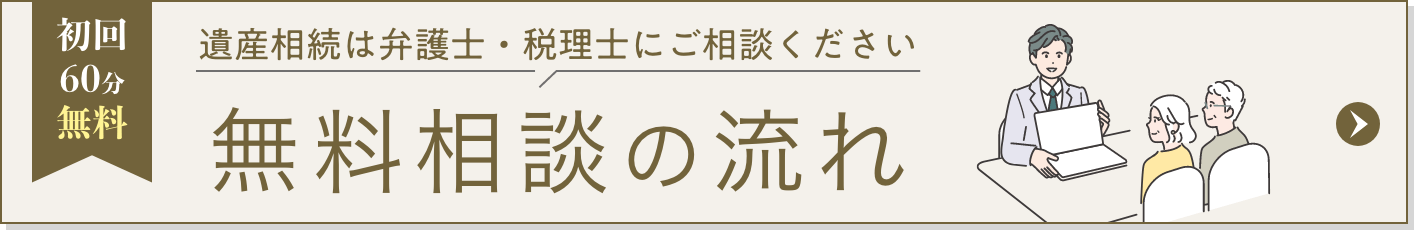
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)
-
2025年12月11日
- 遺産を受け取る方
- マンション
- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年11月27日
- 遺産を受け取る方
- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -
2025年11月19日
- 遺産を受け取る方
- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 相続で利益相反行為が問題になるケースとは? 対処法と注意点を解説


















