- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割協議
- 絶縁中の兄弟姉妹との相続争い|親の相続手続きの進め方と注意点とは
遺産相続コラム
絶縁中の兄弟姉妹との相続争い|親の相続手続きの進め方と注意点とは
- 遺産分割協議
- 相続争い
- 絶縁

親が亡くなり相続が発生すると、子どもは親の相続人として相続手続きをしなければなりません。しかし、さまざまな理由から子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁状態にあるという方もいるかもしれません。
そのような場合、遺産相続において相続争いが発生することも多く、通常の相続手続きとは異なる特別な手続きが必要になる可能性もあります。ご自身での対応が難しいときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
今回は、親の遺産相続にあたり、絶縁している兄弟姉妹の間で相続争いが生じた場合の対処法と注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、被相続人の子どもの相続権とは?
遺産相続において、亡くなった方(被相続人)の子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁している場合、絶縁中の兄弟姉妹にも相続権はあるのでしょうか。
-
(1)被相続人の子どもには相続権がある
親が亡くなったときには、子どもは、第1順位の相続人として遺産を相続することができます。家族と疎遠な関係性であったり、絶縁関係にあったりすることが相続権に影響することはありません。
そもそも法的に絶縁するという制度自体存在しませんので、たとえば被相続人の長男と次男が絶縁していたとしても、どちらにも親の遺産を相続する権利があります。
遺産分割を行うためには、相続人全員の同意が必要です。したがって、絶縁中の兄弟姉妹も含めて、話し合いを進めていかなければなりません。相続人全員の同意がない状態で行った遺産分割協議は無効になりますので注意が必要です。 -
(2)絶縁中の兄弟姉妹に親の遺産を相続させない方法
前述のとおり、法的には絶縁という制度はありません。しかし、以下のような方法により、親が亡くなったときに、絶縁している兄弟姉妹に親の遺産を相続させないようにできる可能性があります。
① 遺言書の作成
遺言書がある場合、相続人による遺産分割協議よりも原則として遺言書の内容が優先されます。そのため、親(被相続人)が生きている間であれば、親(被相続人)が遺言書を作成することによって遺産を相続させないようにできる可能性があります。
ただし、法定相続人である子どもには、最低限の遺産の取得分である遺留分が保障されていますので、遺留分を侵害するような遺言だと、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)をされる可能性があります。そのため、その可能性を十分に検討した上で遺言書を作成する必要があります。
② 相続人廃除
相続人廃除(民法892条)とは、一定の事情がある相続人の相続権を奪うことができる制度です。以下のような事情がある場合、被相続人が生前のうちに遺言または家庭裁判所への申立てをすることで、当該相続人の相続権を奪うことができます。- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- その他著しい非行があったとき
ただし、相続人廃除された相続人に子どもや孫がいる場合には、代襲相続により相続権が引き継がれますので注意が必要です。
③ 相続欠格
相続欠格(民法891条)とは、一定の事由に該当する相続人の相続権が法律上当然に奪われる制度です。以下の相続欠格事由に該当する相続人は、遺留分も含めて一切遺産を相続できなくなります。- 被相続人や他の相続人を殺害した、もしくは殺害しようとした
- 被相続人が殺害されたことを知りながらそれを告発しなかった
- 詐欺や脅迫により遺言を妨げた
- 遺言書を破棄、偽造、隠匿した
前述した相続人廃除は、被相続人による申立てなどの手続きが必要でしたが、相続欠格ではそのような手続きが不要で、当然に相続権が奪われます。
ただし、相続人廃除と同様に、相続欠格により相続権が失われたとしても、当該相続人に子どもや孫がいる場合には、代襲相続により相続権が引き継がれますので注意が必要です。
2、絶縁中の相続人との間で起こり得る相続争いとは?
絶縁している相続人がいる場合、以下のような相続に関する紛争が生じる可能性があります。
-
(1)遺産の割合でもめる
相続人同士が絶縁している場合、円滑に話し合いを進めるのが困難だと考えられます。お互いに自分の意見ばかりを主張した結果、遺産の割合や分け方をめぐって対立し、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。
-
(2)遺産を勝手に処分される
遺産分割協議がまとまらないからといって、そのまま遺産を放置していると、勝手に遺産を処分されてしまうリスクが生じます。たとえば、遺産に不動産が含まれている場合、自己の持分を勝手に第三者に処分してしまい、見ず知らずの第三者との共有になってしまうこともあります。
-
(3)連絡先がわからず遺産分割協議ができない
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。しかし、絶縁中の場合には連絡先がわからず、遺産分割の手続きを進めたくても連絡が取れないため、進められないという事態になることもあります。
-
(4)遺産分割調停・審判により手続きが長期化する
遺産分割について話し合いで解決できないときは、遺産分割調停または審判によって解決を図ることになります。しかし、このような法的手続きが必要になると、相続人同士の話し合いによる遺産分割よりも解決までに時間と労力がかかってしまいます。
3、絶縁中の相続人との相続手続きの進め方
では、絶縁中の相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか。
-
(1)相手の所在がわかっている場合
絶縁していたとしても、相手の所在がわかっている場合には、電話・メール・LINE・手紙などで親が亡くなったことを伝え、遺産分割協議に参加するよう求めてみましょう。
直接会って話をするのが難しいという場合には、電話・メール・LINE・手紙などのやり取りで遺産分割協議を進めることもできます。また、弁護士に依頼をすれば代理人として代わりに対応してもらうことも可能です。 -
(2)相手の所在がわからない場合
相手の所在がわからない場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。そのため、まずは所在調査により相手の所在を調べる必要があります。
所在調査の方法としては、相手の住民票や戸籍の附票を取得するといった方法があります。一般的には、このような所在調査で相手の居所が判明するケースが多いです。しかし、所在調査を実施しても相手の所在がわからないという場合には、以下の手続きを検討することになります。
① 不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人(民法25条)とは、行方がわからない人の代わりに財産を管理する人のことをいいます。絶縁していて相続人の行方がわからないという場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行い、不在者財産管理人の選任をしてもらうことも考えられます。
不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の相続人の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して、遺産分割の手続きを進めることが可能です。
② 失踪宣告の申立て
絶縁中の相続人が行方不明になり、生死不明の状態にある場合には、裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告をされることで、遺産分割の手続きを進めることができます。
失踪宣告(民法30条)とは、一定の要件を満たす行方不明者を法律上、死亡したものとみなすことができる制度です。一般的に用いられる失踪宣告は、「普通失踪」と呼ばれる制度で、7年間生死不明の状態が続くと、7年を経過した日に死亡したものとみなされます。
失踪宣告により死亡したものとみなされた場合には、当該相続人を除いて遺産分割協議を進めることができます。ただし、当該相続人に子どもや孫がいる場合には、その人を遺産分割協議に参加させる必要がある点に注意が必要です。 -
(3)遺産分割調停・審判
相続人同士での遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。調停では、裁判官や調停委員が関与して話し合いを進めてくれますので、お互いに冷静に話し合いを進めることができます。
ただし、調停は、あくまでも話し合いの手続きになりますので、相続人全員の合意が得られない場合は調停不成立となってしまいます。調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、遺産分割方法を決定します。
4、相続手続きを進める際の注意点・ポイント
相続手続きを進める際には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)相続手続きが終わるまでは遺産に手を付けない
相続手続きが完了するまでは、相続財産は相続人全員の共有状態ですので、遺産を処分するには、相続人全員の同意が必要になります。そのため、自分の判断だけで遺産を処分することはできません。
万が一勝手に遺産を処分してしまうと、遺産の使い込みを疑われて紛争が激化してしまう可能性もありますので、相続手続きが終わるまでは遺産に手を付けないようにしてください。 -
(2)絶縁中の相手とのやり取りはできるだけ冷静に対応する
絶縁することになった理由によっては、相手との話し合いで感情的になってしまい、言い争いに発展することもあります。しかし、感情的な話し合いでは適正な遺産分割を実現することは困難ですので、できるだけ冷静に対応するようにしましょう。
当事者だけで話し合いをするのが難しいという場合には、弁護士に依頼するのもおすすめです。 -
(3)弁護士に代理人を依頼する
絶縁中の相手との間で相続争いが生じた場合は、弁護士に代理人を依頼するとよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、本人に代わって弁護士が相手との交渉を行いますので、冷静に話し合いを進めることができます。また、相手の所在がわからないという場合でも、弁護士が所在調査を実施して明らかにすることができます。ほかにも、不在者財産管理人の申立てや失踪宣告の手続きも任せることができます。
絶縁中の相手とのやり取りが不安だという方は、弁護士に相談するようにしましょう。
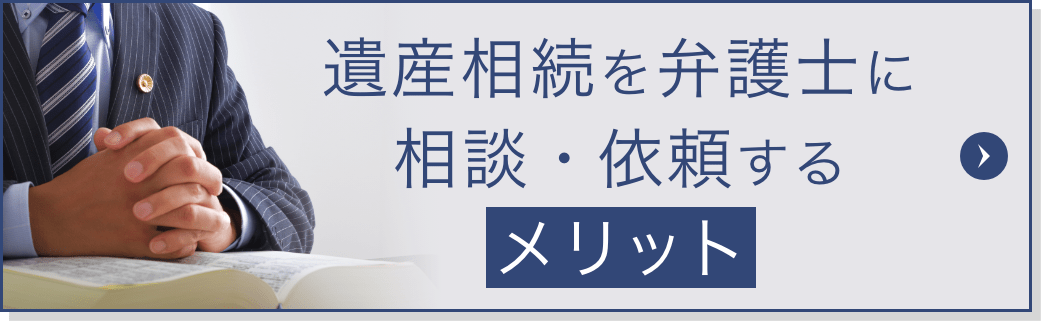
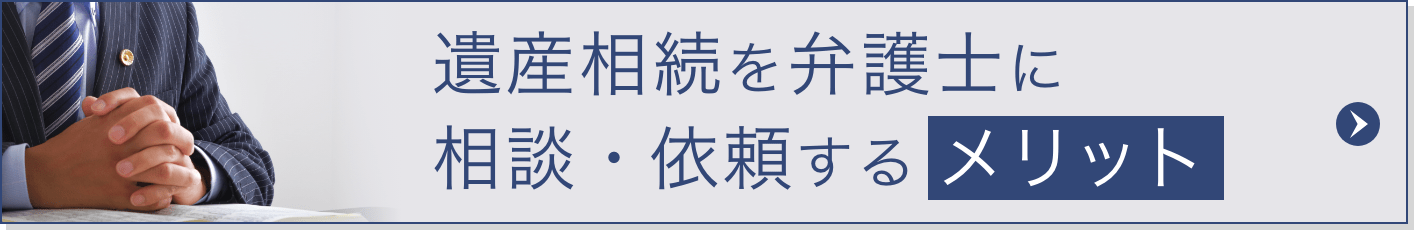
60分無料
5、まとめ
親が亡くなった場合、子どもには相続権が認められます。そのため、たとえ子ども同士が絶縁していたとしても、相続人全員で遺産相続の手続きを進めていかなければなりません。しかし、絶縁理由によっては、当事者同士の話し合いだと相続争いに発展する可能性もありますので、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
絶縁している相続人との遺産分割は、弁護士に依頼することで負担を大幅に軽減することができます。まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産分割協議)
-
2025年12月15日
- 遺産分割協議
- 隠し子
- 相続

親が亡くなったあとに、知らされていなかった「隠し子」の存在が明らかになることがあります。こうしたケースで「隠し子にも相続権があるのか」と戸惑うご家族も少なくありません。
結論から言うと、被相続人(亡くなった方)から認知されている場合、隠し子であっても相続人です。ただし、血縁上は親子であっても相続人とならない例外も存在し、個別の状況によって対応が異なります。
今回は、隠し子がいた場合の相続について、例外となるケースや、具体的な相続手続きの流れを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。 -
2025年09月11日
- 遺産分割協議
- 再転相続

法定相続人が相続の承認、または相続放棄の意思表示をすることなく熟慮期間中に亡くなった場合、再転相続が発生します。
再転相続は、遺産分割が完了する前に次の相続が発生する数次相続とは異なり、まず当初の相続についての承認または相続放棄を検討しなければなりません。また、再転相続の状況によっては、熟慮期間中であっても相続放棄が認められないケースもありますので、注意が必要です。
今回は、再転相続とは何か、再転相続が発生する具体的なケースや熟慮期間の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年03月19日
- 遺産分割協議
- 同時死亡の推定

交通事故や自然災害などにより家族を同時に複数名失ってしまった場合、亡くなった方(被相続人)の遺産はどのように相続すればよいのでしょうか。
交通事故などで誰が先に亡くなったのかがわからない場合には、「同時死亡の推定」が働き、同時に死亡したものと推定されます。同時死亡と推定されるか否かによって、遺産相続や相続税に大きな違いが生じますので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、同時死亡の推定の考え方や具体的なケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産分割協議
- 絶縁中の兄弟姉妹との相続争い|親の相続手続きの進め方と注意点とは


















