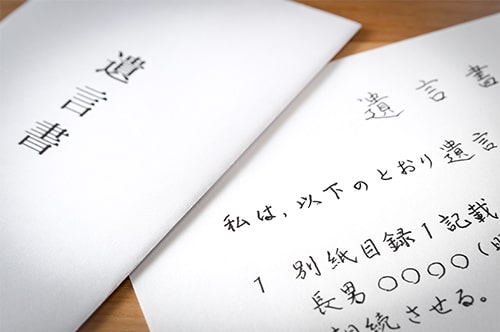- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 父の遺産を母が独り占め! 独占のデメリットと子の立場からの対抗策
遺産相続コラム
父の遺産を母が独り占め! 独占のデメリットと子の立場からの対抗策
- 遺留分侵害額請求
- 父の遺産
- 母が独り占め

遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしてトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
たとえば父の遺産を母が独り占めしようとしていて、それを子どもの立場から阻止したい場合、適切な対応をとることが必要です。
本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしているとき、子どもの立場からできる対抗策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、父の遺産を母が独り占めすることは場合によっては違法ではない
母が父の遺産を独り占めすることはできるのでしょうか。以下では、相続に関する基本事項と母がすべての遺産を相続できるケースについて説明します。
-
(1)相続人と相続割合
被相続人が死亡した場合には、その相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を相続することになります。その際に誰が相続人になるのかについては、民法で以下のように定められています。
- 被相続人の配偶者は常に相続人になる
- 被相続人の子どもは第1順位の相続人
- 被相続人の直系尊属(父母が存命なら父母、父母は死去しているが祖父母は健在であれば祖父母になります)は第2順位の相続人
- 被相続人の兄弟姉妹は第3順位の相続人
また、各相続人の相続割合については、誰が相続人になるかによって以下のように異なってきます。
①配偶者、子ども、父母のどちらか、兄弟姉妹などの相続人がひとりのみ
このケースでは、相続人はひとりしかいないので、相続人となるひとりの方がすべての遺産を相続することができます。
②配偶者と子ども
このケースでは、配偶者の相続割合が2分の1、子どもの相続割合が2分の1となります。子どもが複数いる場合には、2分の1の相続割合を子どもの人数でさらに等分します。
③配偶者と父母
このケースでは、配偶者の相続割合が3分の2、父母の相続割合が3分の1となります。父母がどちらも健在という場合には、3分の1を2人で分けることになるため、父が6分の1、母が6分の1の相続割合となります。
④配偶者と兄弟姉妹
このケースでは、配偶者の相続割合が4分の3、兄弟姉妹の相続割合が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1の相続割合を兄弟姉妹の人数でさらに等分します。 -
(2)母にすべての遺産を渡すことが可能となるケース
上記のように相続人には法定相続分が定められています。したがって、基本的には、遺産を母が独り占めすることはできません。
しかし、以下のようなケースであれば、父の遺産を母が独り占めすることも可能です。
①遺言書で母にすべての遺産を相続させると書かれているケース
父が遺言書に「妻にすべての遺産を相続させる」と記載していた場合には、有効な遺言であれば、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されますので、母が父の遺産を独り占めすることができます。
ただし、この場合には、他の相続人(ただし、兄弟姉妹は除く)が遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。したがって、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権の行使があった場合、母は、遺留分を侵害した額に相当するお金を渡さなければなりません。
②相続人全員の合意により母にすべての遺産を相続させるケース
遺言書がない場合には、被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議によって分割方法を決めていくことになります。遺産分割協議の結果、父の遺産を母がすべて相続することについて相続人全員が合意をした場合には、母が独り占めすることができます。
60分無料
2、母がすべて相続した場合に起こり得るデメリット
母がすべての遺産を相続した場合には、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
-
(1)二次相続の税金問題
二次相続とは、一次相続で相続人になった配偶者が亡くなった場合に発生する相続のことをいいます。たとえば、父、母、子どもという家族の場合、父が死亡した場合に、母と子が相続人になる相続を「一次相続」といい、その後、母が死亡した場合に、子が相続人になる相続を「二次相続」といいます。
一次相続において、父の遺産を母が独り占めすることになった場合には、二次相続で相続人が負担する相続税の金額が非常に高額になるおそれがあります。その理由は、相続税の配偶者控除の利用の有無です。
配偶者控除は、以下の2つのうち、どちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。- 配偶者の取得する遺産額1億6000万円まで
- 配偶者の法定相続分相当額
一次相続では、相続人に配偶者が含まれるため配偶者控除を利用することができますが、二次相続の相続人は配偶者ではないため、配偶者控除を利用することはできません。
母が父の遺産を独り占めした場合、二次相続では一次相続で相続した父の遺産と母の遺産を加算した状態で相続人に引き継がれることになります。財産額は一次相続より高額になる可能性があるにもかかわらず、二次相続では配偶者控除を利用することができません。
また、一次相続より二次相続の方が相続人の人数が減少するのが通常であるため、基礎控除額が減額になり、課税される遺産の総額が高くなる結果、相続税額も高くなることとなります。
そのため、一次相続では二次相続のことも考慮したうえで、遺産分割方法を決めていくことが大切なポイントとなります。 -
(2)遺産相続に関するトラブルの発生
父の遺産を母が独り占めするという遺産分割方法は、民法が定める法定相続分とは異なる割合での遺産相続になります。そのため、本来もらえるはずだった遺産を相続できなかった相続人から不満が出ることが予想されます。
母が遺産を独り占めすることについて、すべての相続人が納得していればもちろん問題ありません。しかし、そうでない場合には、遺産分割調停や審判、遺留分侵害額請求、使途不明金をめぐる民事訴訟などに発展する可能性があります。

3、ひとりの相続人が遺産を独り占めするのを防ぐ3つの方法
ひとりの相続人が遺産を独り占めすることを防ぐ方法としては、以下の方法があります。
-
(1)遺留分侵害額請求
相続人には、法律上、最低限の遺産の取得割合として遺留分が保障されています。
つまり、父が母にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していた場合には、他の相続人の遺留分が侵害されることになるのです。そこで、遺留分を侵害された相続人は、母に対して遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当するお金の返還を求めることができます。
ただし、遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年以内に行使することが必要です。 -
(2)遺言無効確認訴訟
父が作成した遺言書に形式上の不備があったり、判断能力がない状態で作成された疑いがあったりする場合には、遺言無効確認訴訟を提起して、遺言書の有効性を争うことが可能です。
遺言書が無効と判断された場合には、父の遺産は、相続人全員の遺産分割協議によって分けることになりますので、母による遺産の独り占めを防止することができます。 -
(3)預貯金口座の凍結
遺産の独り占めをしようとした相続人が、他の相続人にバレないように遺産を使い込んでしまうケースもあります。遺産の使い込みがあった場合には、それを取り戻すために多大な労力を要することになりますので、まずはできる限り事前に防ぐことが大切です。
預貯金であれば、金融機関に対して口座名義人が死亡したことを知らせると、預貯金口座を凍結することが可能です。被相続人名義の口座凍結の手続きを迅速に行うことで、遺産の使い込みを防止できます。
また、分割に応じたように見せかけて、口座や株、現金、不動産の登記済証(権利書)などを隠している可能性もあるため、遺産分割の際には相続財産をしっかりと調査することが重要です。
60分無料
4、母が父の遺産を隠しているときの対応方法
母が父の遺産を隠している疑いがある場合には、以下のような対応が必要となります。
-
(1)遺産の調査方法
遺産隠しの疑いがある場合には、遺産の種類に応じて以下のような調査方法が考えられます。
①預貯金の調査方法
被相続人名義の預貯金口座については、相続人であれば誰でも調べることが可能です。被相続人が口座を開設している可能性のある金融機関で、相続人であることを証明できる資料を提出して、残高証明書や取引履歴などを発行してもらうとよいでしょう。
②不動産の調査方法
被相続人が不動産を所有している場合には、市区町村役場で名寄帳(固定資産課税台帳)の発行を受けることで、当該市町村内にあるすべての所有不動産を知ることができます。名寄帳で開示できるのは、その市町村内の分のみになりますので、他の市町村にも不動産がある可能性がある場合には、その不動産が存在している市区町村役場で申請する必要があります。
③株式の調査方法
株式や投資信託については、被相続人が取引をしていた証券会社に問い合わせをすることによって資産状況を開示してもらうことができます。取引していた証券会社がわからないという場合には、証券保管振替機構に問い合わせ、登録済加入者情報の開示請求を行うとよいでしょう。 -
(2)遺産の使い込みが判明した場合の対応方法
相続人による遺産の使い込みが判明した場合には、以下のような対応が必要になります。
①相手との話し合い
遺産の使い込みが判明した場合には、遺産の使い込みをした相続人と話し合いを行い、使い込んだ遺産の返還を求めます。使い込みをした相続人は、使い込みを否定するケースが多いため、相手が使い込みをしたという証拠を話し合いの前にしっかりと集めておくようにしましょう。
②裁判
遺産の使い込みをした相続人が使い込みを認めない場合には、裁判を起こす必要があります。使い込みの裁判をする場合の法律構成としては、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の2つがあります。
どちらの構成で請求するかによって時効期間が異なってきますので、使い込みの裁判をする場合には専門家である弁護士に相談をしながら進めていくようにしましょう。

5、説得が難しいときや解決が困難なときは弁護士に相談を
母が正当な理由なく遺産を独り占めにしようとしている場合には、法定相続分に基づく遺産分割を求めていくことになります。しかし、場合によっては、家族からの説得には耳を貸さない、というケースがあることは否定できません。
そのような場合には弁護士が相続人の代理人として交渉をすることによって、説得に応じてくれる可能性があります。当事者同士だとどうしても感情的になってしまいますが、弁護士であれば法的根拠に基づいて冷静に説得しますので、適切な解決が期待できるでしょう。
なお、遺産分割自体には期限はありません(ただし、令和5年4月からは、一定期間経過後には特別受益や寄与分の主張ができなくなります。)が、相続放棄をする場合には3か月以内、相続税の申告は10か月以内など、期限がある手続きもあります。したがって、相続が発生した場合には、すぐに遺産分割の手続きに着手すべきです。期限を超過してしまうとさまざまなペナルティーを受ける可能性も出てきますので、素早く対応していかなければなりません。
当事者同士での解決が難しいと感じた場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
60分無料
6、まとめ
相続人には、法定相続分がありますし、一定の範囲の相続人には遺留分も認められています。そのため、父の遺産を母が独り占めしようとしても、基本的には認められません。
正当な理由なく遺産の独り占めをしようとしている相続人がいる場合、すぐに適切な対応をとらなければ、遺産の使い込みなどのリスクが生じます。
当事者だけで解決困難な問題に直面した場合には、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。遺産相続専門チームの弁護士が親身にお話を伺いながら、問題を解決できるように尽力いたします。
なお、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っておりますので、ご希望の際はご予約時にお知らせください。
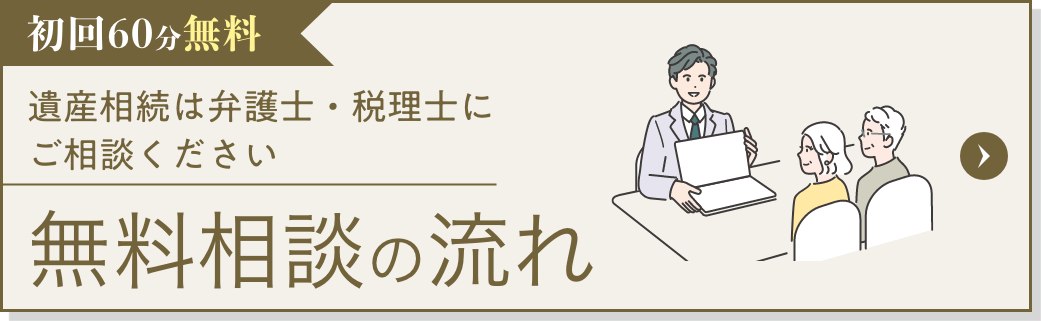
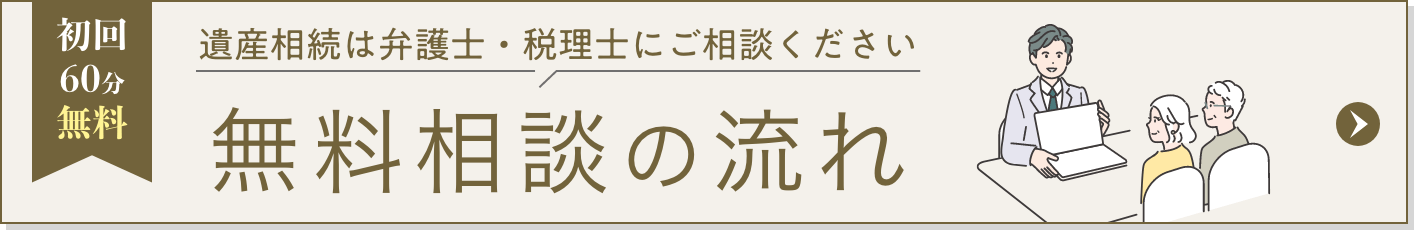
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)
-
2026年01月07日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年10月15日
- 遺留分侵害額請求
- 遺言書
- 全財産
- 無効
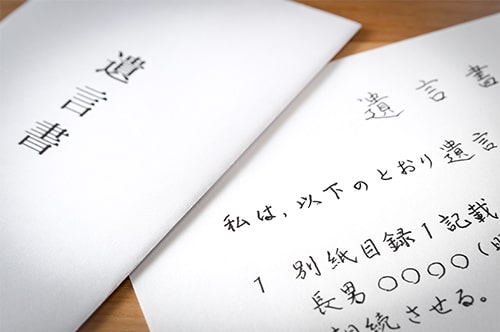
「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年07月23日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求
- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 父の遺産を母が独り占め! 独占のデメリットと子の立場からの対抗策