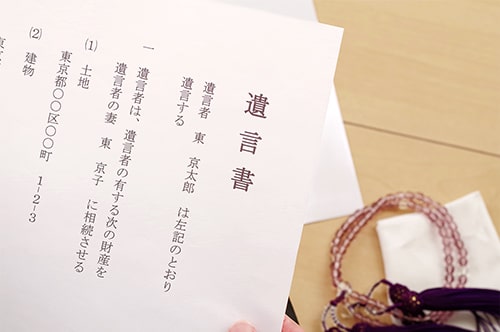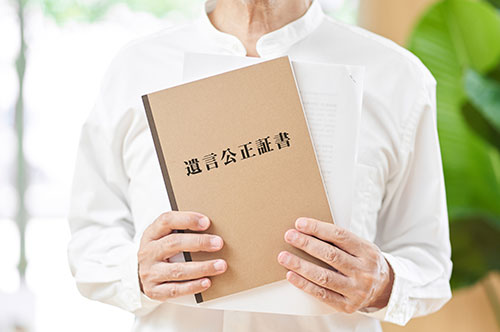- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺言
- 遺言書の偽造が疑われるときの対処法とトラブル回避策
遺産相続コラム
遺言書の偽造が疑われるときの対処法とトラブル回避策
- 遺言
- 遺言書
- 偽造
- トラブル回避
- 対処法

自筆証書遺言は、偽造や変造のおそれがある点が大きなデメリットといえます。
万が一、誰かしらに遺言書が偽造された場合、その遺言書に基づいて遺産分割がなされてしまうと不公平なものになってしまうおそれがあるでしょう。
その際は、適切な手続きを踏んで遺言の無効を争うことになります。
本コラムでは、遺言書の偽造が疑われるときの対処法や刑事罰、損害賠償請求などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、偽造・変造されやすい自筆証書遺言
民法では、遺言の種類として、普通方式遺言(民法967条以下)と特別方式遺言(民法976条以下)が定められています。以下では、主に普通方式遺言について説明します。
普通方式遺言の方式は3つあります。その中でも自筆証書遺言は作成しやすい一方で、偽造や変造されるおそれも高いため、注意が必要です。
-
(1)普通方式遺言の3つの方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)
普通方式遺言には、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3つの方式が認められています。
① 自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印することによって、遺言書を作成します。
② 公正証書遺言(民法第969条)
⑴証人2人以上の立会いの上、⑵遺言者から公証人に対し遺言の趣旨を口授し、⑶公証人から遺言者に対し、口授について筆記したものを読み聞かせるか閲覧させ、⑷遺言者と証人がその筆記が正確なことを承認した後で署名押印し、⑸公証人が⑴から⑷の方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印することによって、遺言書を作成します。
③ 秘密証書遺言(民法第970条)
⑴遺言者が証書に署名押印し、⑵証書を封入の上、封印し、⑶公証人1人及び証人2人以上に対し、その封書を提出し、自己の遺言書であること、筆者の氏名、住所を申述し、⑷公証人がその封書の提出日、遺言者の申述について封紙に記載した後、遺言者と証人が署名押印することによって、遺言書を作成します。 -
(2)自筆証書遺言が偽造または変造されやすい理由
上記の3つの遺言書の方式の中で、自筆証書遺言は、公証人によるチェックが唯一行われません。
そのため、遺言者以外の者が、遺言者が作成したものと偽って自筆証書遺言を偽造するケースは起こり得るといえます。
また、原本が公証役場に保管される公正証書遺言や、証書が封印される秘密証書遺言と比較して、自筆証書遺言は内容を書き換えることが容易という側面もあります。
自筆証書遺言が偽造・変造されてしまうと、遺言者の意思が相続の中で適切に実現しないばかりか、特定の相続人が不利益を被ることにもなりかねません。
2、遺言書の偽造または変造を証明する方法
自筆証書遺言の偽造または変造を証明するためには、筆跡やその他の事情から、遺言者本人が書いたものではないことを示す必要があります。
-
(1)筆跡が争点になることが多い
遺言者自身が書いたものかどうかを判断するに当たって、重要な考慮要素となるのが筆跡です。筆跡には個人のクセや特徴が表れるため、専門鑑定人による筆跡鑑定を行うことによって、遺言者以外の者が自筆証書遺言書を作成したことを証明できる場合があります。
実際に過去の裁判例においても、筆跡鑑定の結果、遺言書の偽造が認定されたケースがあります(高松高裁 平成25年7月16日判決など)。 -
(2)遺言書の偽造を示すその他のポイント
筆跡以外に、遺言書が偽造されたことの証明につながる要素としては、次のような事柄があげられます。
● 遺言書作成時点での遺言者の自書能力の存否及びその程度、遺言内容の複雑性等
遺言書作成時点で、被相続人の認知能力が相当悪化していたにもかかわらず、かなり詳細かつ複雑な内容で遺言書が作成されている場合など。
● 遺言書の保管状況及び発見状況等
遺言者と疎遠な親族が遺言書を発見した場合や、通常想像ができないような場所から遺言書が発見された場合など。
● 遺言書それ自体の体裁等
遺言書の用紙がそれぞれのページで異なり、遺言書に記載されている文字の色合い、濃淡が異なり、文書形式や言葉遣いが異なる場合など。
● 遺言の動機及び理由、遺言者と相続人または受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯等
被相続人と疎遠であったはずの親族などに対して、多額の遺贈が行われているなどの事情がある場合など。
60分無料
3、偽造が疑われる遺言書が見つかった場合の対処法と流れ
思いもよらない形で自筆証書遺言書が発見され、偽造が疑われる場合には、まず家庭裁判所の「検認」を経て、それから遺言無効確認訴訟の提起を検討しましょう。
-
(1)家庭裁判所の検認を経る
自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の保管者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に対して当該遺言書の検認を申し立てなければなりません(民法第1004条第1項)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日時点における遺言書の状態を確定し、遺言書の偽造または変造を防止するための手続きをいいます。検認の際には、あくまでも遺言書の状態の明確化が行われるのみであって、遺言の有効・無効について判断されるわけではありません。
なお、自筆証書遺言書は、家庭裁判所による検認を経ない限り、相続人などが勝手に開封することは禁止されています。遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り、検認を経ないで自筆証書遺言書を開封した場合には、「5万円以下の過料」に処される可能性があるので注意しましょう(民法第1005条)。 -
(2)訴訟を提起して遺言無効の確認を求める
検認手続きの中で、相続人は自筆証書遺言書の内容を確認することができます。
その段階で、偽造の疑いを持った場合には、裁判所に対して訴訟を提起し、遺言無効の確認を求めましょう。
遺言無効確認訴訟では、筆跡を中心として、遺言の偽造または変造が疑われる事情について主張・立証を行う必要があります。訴訟における主張・立証活動には、事前の法的な検討が不可欠です。訴訟手続きを遂行する手間も考えると、弁護士に相談した上で対応するのがよいでしょう。
4、遺言書の偽造または変造は犯罪に当たる? 損害賠償請求は可能?
遺言書を偽造または変造した場合、当該遺言書が無効になることはもちろんですが、刑事上および民事上のペナルティーを受ける可能性があるほか、相続権を失うこともあります。
-
(1)遺言書の偽造は「有印私文書偽造罪」に該当する
刑法上、遺言書の偽造は「有印私文書偽造罪」に該当します(刑法第159条第1項)。有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
また、遺言書を変造した場合にも、同様の刑罰が科されます(同条第2項)。 -
(2)遺言書の偽造は「相続欠格事由」にも該当する
遺言書の偽造、変造、破棄または隠匿は、相続人の欠格事由とされています(民法第891条第5号)。相続欠格事由に該当した場合、相続欠格者は相続権を喪失します。
ただし、相続欠格事由に該当した者に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続します(民法第887条、889条第2項)。 -
(3)相続人や受遺者が損害を受けた場合には損害賠償請求が可能
遺言書の偽造によって、相続人や受遺者が損害を受けた場合には、偽造者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できる場合があります(民法第709条)。
60分無料
5、遺言書の偽造または変造を防ぐための対策
遺言書の偽造または変造・紛失を防ぐためには、公正証書遺言を作成する方法、あるいは法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法が有効です。
-
(1)公正証書の方式で遺言書を作成する
公正証書遺言は、遺言者自身が公証役場において公証人に遺言の内容を伝え、その内容に基づいて作成されます。
公正証書遺言の原本は公証役場において保管されるので、相続人その他の親族などによって、遺言書が偽造または変造される心配もありません。参考:公正証書遺言作成の流れ
-
(2)法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは、令和2年(2020年)7月10日から開始された新しい制度です。法務局において、自筆証書遺言書を保管してもらうことができます。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、遺言者本人が手続きを行う必要があり、法務局における本人確認も行われます。また、自筆証書遺言者の手元で保管する場合とは異なり、法務局で原本が保管されます。そのため、相続人その他の親族などによって自筆証書遺言書が偽造または変造されるおそれもありません。
6、まとめ
遺言書が偽造または変造されてしまうと、不利益を被る相続人が出てしまうことにもなりかねません。さらに、遺言者の意思が正しく実現されないことにもなります。
遺言書の偽造または変造が疑われる場合には、遺言書の無効確認訴訟を見据えて、弁護士に相談しながら対応することがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は遺産相続専門チームを組織しており、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍しています。遺言書に関するあらゆるトラブルを解決へと導きますので、遺産相続トラブルにお悩みの方や遺言書作成にご関心をお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺言)
-
2025年01月09日
- 遺言
- 相続
- 遺言書がある場合
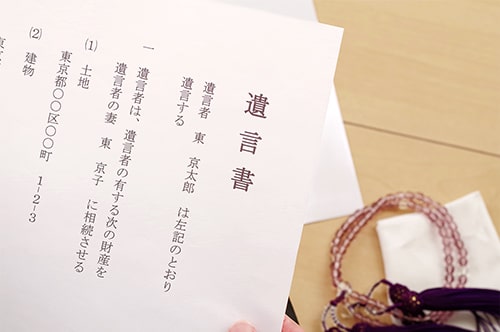
遺言書を残して亡くなった方がいた場合、原則として、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合の相続には注意点がありますので、しっかりと押さえておきましょう。
また、遺言書の内容が不公平な内容であった場合、遺留分侵害額請求ができる可能性もあります。この遺留分侵害額請求には、期限が設けられていますので、遺留分の侵害を知ったときは早めに行動することが大切です。
今回は、遺言書がある場合の相続の進め方と不公平な遺言への対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年12月05日
- 遺言
- 負担付遺贈

負担付遺贈とは、財産を譲り渡す代わりに、遺贈を受ける人に対して、一定の義務を負担させる遺贈のことをいいます。自分が亡くなった後、妻の世話やペットの飼育を頼みたいという希望がある場合など、負担付遺贈を利用することによって、希望をかなえることができる可能性があります。
ただし、負担付遺贈をする場合には、いくつか注意すべきポイントがありますので、それらをしっかりと押さえておくことが大切です。
本コラムでは、負担付遺贈の概要や作成時の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年03月14日
- 遺言
- 公正証書遺言
- もめる
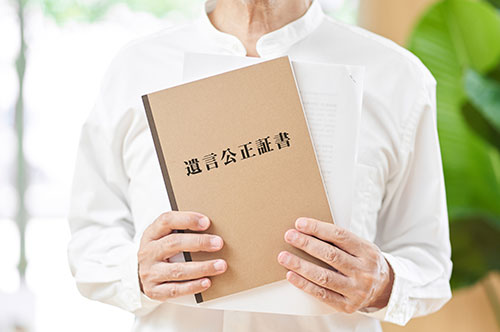
公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べてトラブルになるリスクが低い遺言書だと言われています。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言書の形式や内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお考えの方は、遺言書が無効にならないようにするためのポイントを押さえておくことが大切です。
今回は、将来の遺産相続トラブルを防止するため、公正証書遺言作成のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺言
- 遺言書の偽造が疑われるときの対処法とトラブル回避策