- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 生命保険金は相続財産? 受取人・他の相続人の平等な相続は実現可能?
遺産相続コラム
生命保険金は相続財産? 受取人・他の相続人の平等な相続は実現可能?
- 遺産を受け取る方
- 生命保険
- 相続財産

親などの家族が亡くなってしまった場合、生命保険に加入していれば、受取人が生命保険金を一括で受け取ることになります。
しかし、生命保険金の受取人として相続人全員が指定されることは極めて稀で、一部の相続人のみが生命保険金を受け取るよう指定されている場合がほとんどです。死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないため、遺産分割の対象とならず、受取人本人の財産となります。
生命保険金の受取人が他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたり、生命保険の金額が多額であったりする場合には、ほかの相続人としては不公平を感じてしまうでしょう。
こうした相続人間の不公平を是正するための相続法上の考え方として、「特別受益」「寄与分」「遺留分」というものがあります。
本コラムでは、生命保険金の受け取りが絡む場合に、どのように公平・平等な遺産相続を実現することができるかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、生命保険金は相続財産になる?
生命保険金を受け取ることができるのは受取人ですが、そもそも掛け金の負担者は契約者です。亡くなった被相続人が被保険者となって掛けられている生命保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか。
-
(1)原則として生命保険金は相続財産ではない
最高裁判所は、死亡保険金請求権(生命保険金)は原則として相続財産に含まれないと判断しました。生命保険金請求権は、保険契約に基づいて保険金受取人が自らの固有の権利として取得することを理由としています。
生命保険金が支払われる場合にも、受取人が自らの財産として受け取るのであって、亡くなった方(被相続人)の財産となることは原則としてありません。 -
(2)生命保険金が例外的に相続財産として扱われるケースとは
原則として、生命保険金は相続財産にはなりませんが、生命保険金の受取人が被保険者本人である場合には相続財産となります。生命保険の場合には非常に稀ではありますが、受取人を本人としているようなケースでは、生命保険金は死亡した本人の財産となるため、例外的に相続財産に含まれます。
60分無料
2、生命保険金の受取人と他の相続人の間で平等な相続を行うには?
生命保険金を一部の相続人しか受け取れない場合(たとえば、ひとりで全額を受け取る場合など)、他の相続人からすると不公平・不平等に感じられるでしょう。
このような場合に、相続人間の不公平・不平等を是正する方法として、考えられるものをいくつか紹介します。
-
(1)生命保険金を特別受益として相続財産に持ち戻す
まず、「特別受益」の考え方を使って、生命保険金相当額を相続財産にプラスする(持ち戻す)方法が考えられます。
特別受益とは、相続人が以下の遺贈または贈与により被相続人から受けた利益をいいます。- 遺贈(全般)
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
特別受益がある場合には、各相続人の法定相続分を計算するにあたって相続財産の金額に加算されますので(民法第903条第1項)、特別受益を受けた人以外の相続人の取り分が増えることになります。
しかし、生命保険金請求権は保険契約に基づいた受取人の固有の権利であることや、払い込んだ保険料と等価関係にないことなどを理由に、原則として遺贈または贈与の財産に当たらないとされています。ただ、生命保険の保険料を被相続人が支払っていた場合には、実質的に見れば被相続人から受取人に対する遺贈または贈与に近い性質を有すると言うことが可能です。
そのため、最高裁判所は、保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生ずる不公平が著しい場合には、例外的に民法903条1項を類推して、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合があると判断しました(最判平成16年10月29日)。
受取人とほかの相続人との間の不公平が著しいといえるかどうかは、以下の要素などを総合的に考慮して判断されます。- 保険金の額
- 保険金額の、遺産の総額に対する比率
- 相続人と被相続人の関係(同居の有無、介護等に対する貢献度など)
- 各相続人の生活実態
-
(2)他の生前贈与・遺贈を特別受益として相続財産に持ち戻す
生命保険金を受け取ることが特別受益に該当しない場合であっても、他に特別受益に該当する遺贈や贈与が存在する場合には、これを相続財産に持ち戻すことによって、相続人間の不公平を是正することができます。
たとえば、被相続人から相続人に対して住宅購入用資金が贈与されていた場合には、特別受益に該当する可能性が高いといえるでしょう。 -
(3)特に貢献のあった相続人については寄与分を定める
生前の被相続人の財産の維持または増加に対して特に貢献のあった相続人については、「寄与分」を定めることにより、遺産分割の際に優遇することができます(民法第904条の2第1項)。
寄与分が認められる例としては、被相続人に対して以下の貢献を行った相続人です。- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 財産上の給付
- 被相続人の療養看護
- その他の方法による被相続人の財産の維持または増加についての貢献
寄与分相当額は、法定相続分を計算する際には相続財産からあらかじめ控除され、そのまま寄与分を有する相続人の取り分となります。
寄与分が認められる要件は、上記以外にもあり、実務上認められることも難しいことがあります。上記に該当する場合には、弁護士にご相談ください。
60分無料
3、生命保険金を特別受益としたとき、遺留分はどう計算する?
特別受益は、遺留分の計算においても考慮されます。生命保険金が特別受益として取り扱われる場合、どのように遺留分が計算されるかについて解説します。
-
(1)遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる「最低限相続できることが保障された金額」をいいます。
被相続人は、遺言書を作成することによって、法定相続分とは異なる割合による相続分の指定を行うことが可能です。しかし、遺言書の内容によっては、ある相続人について遺留分の金額よりも少ない財産しか分け与えないとされている場合もあります。
この場合、相続人は遺留分の侵害を主張して、他の相続人に対して侵害分の金銭を請求することが可能で(民法第1046条第1項)、これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分の金額は、法定相続分を基準として算出されます。具体的には、以下のとおりです(民法第1042条第1項)。- 直系尊属(父母など)のみが相続人である場合……法定相続分の3分の1
- それ以外の場合……法定相続分の2分の1
各相続人の法定相続分は、相続財産の金額を基準として算出されます。
-
(2)特別受益は相続開始前10年間にされた場合に限り考慮される
遺留分計算にあたっては、相続人に対して相続開始前10年以内に贈与された財産の金額も相続財産に持ち戻されます(民法第1044条第1項、第3項)。
前述のとおり、生命保険金が特別受益とみなされる場合、上記の規定に従い、遺留分計算の際に考慮されます。 -
(3)生命保険金が特別受益に当たる場合の遺留分の計算例
モデルケースを用いて、実際に生命保険金が特別受益に当たる場合の遺留分を計算してみましょう。
<設例>
- 被相続人Xが死亡
- 相続人は配偶者Aと子どもB・Cの3名
- 相続財産は合計1200万円
- X死亡に伴い、Bが2800万円の生命保険金を受け取った(特別受益に該当)
上記の例では、実際の相続財産は1200万円ですが、Bの受け取った2800万円の生命保険金が特別受益に該当するため、これを相続財産に加算(持ち戻し)します。
すると、計算上、相続財産とみなされる金額は1200万円+2800万円=4000万円です。この4000万円を基準として、A・B・Cの遺留分を計算します。遺留分の計算式は以下のとおりです。遺留分=相続財産の金額×法定相続分×遺留分の割合
Aの遺留分
4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
Bの遺留分
4000万円×4分の1×2分の1=500万円
Cの遺留分
4000万円×4分の1×2分の1=500万円
上記の遺留分金額と、実際にA・B・Cが受け取る相続財産の金額を比較します。まず、法定相続分に従って計算したA・B・Cの相続分は以下のとおりです。
Aの相続分
4000万円×2分の1=2000万円
Bの相続分
4000万円×4分の1=1000万円
Cの相続分
4000万円×4分の1=1000万円
しかし、実際には相続財産は1200万円しかありませんので、A・B・Cの実際の相続金額は以下のとおりとなります。
A:800万円
B:0円(+生命保険金2800万円)
C:400万円
これを遺留分の金額と比較すると、Aについては200万円(本来の遺留分1000万円―実際の相続金額800万円)、Cについては100万円(本来の遺留分500万円―実際の相続金額400万円)が不足しています。
したがって、AとCは、それぞれBに対して不足分の金銭を請求することが可能です。
4、遺産相続で生じる相続税の相談は専門家へ
上記で解説した法律上の問題に加えて、遺産相続の処理を行う際には、相続税(生前贈与をする場合は贈与税も)についても考慮しておく必要があります。
相続税には、以下の金額の基礎控除(非課税枠)が設けられており、相続財産がこの金額に収まっている場合には、相続税を納める必要はありません。
しかし、基礎控除額を上回る相続財産が存在する場合には、相続税の課税対象となります。
なお、被相続人が会社などに勤めていた場合は死亡退職金が給付されることがあります。
相続税の計算時には、相続財産に死亡退職金が含まれてしまうことに注意が必要です。
相続税の計算は非常に複雑なので、相続人の方々だけでこれを行うことは困難です。そのため、弁護士や税理士などの専門家に相談の上対応することをおすすめします。
60分無料
5、まとめ
生命保険金は原則として相続財産に含まれません。しかし、生命保険金の受取人が被保険者本人である場合には、例外的に相続財産となります。
生命保険金が相続財産に含まれないケースでは、特別受益や寄与分、遺留分の制度を活用することで、相続人間の不公平をある程度是正できる可能性があるため、弁護士に相談することがおすすめです。
また、遺産相続においては法律上の問題と同時に、相続税も重要な課題となります。
ベリーベスト法律事務所では、相続に関するご相談に際して、必要に応じてグループ内に所属する税理士が同席いたします。法律・税務の両面から万全に相続手続きを進めたいという方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。知見豊富な士業が誠心誠意、サポートいたします。
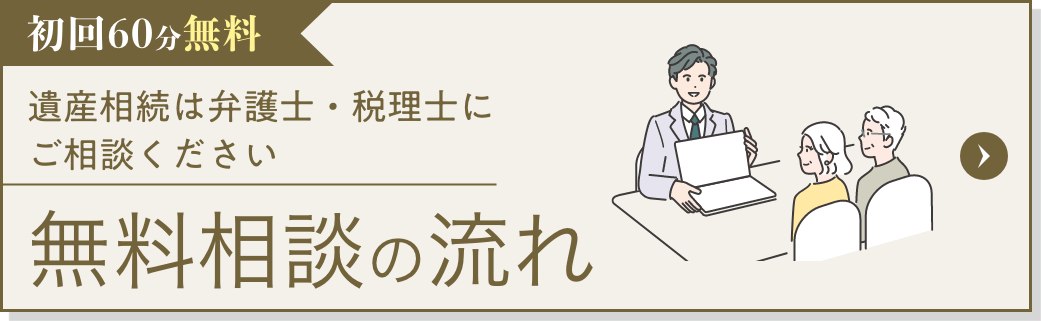
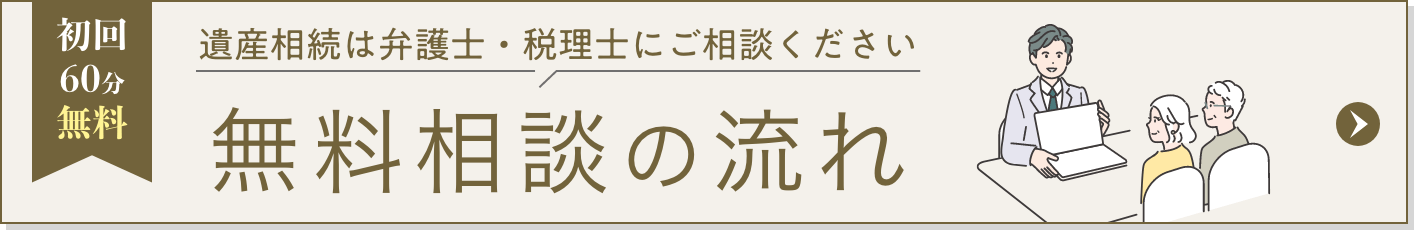
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)
-
2025年12月11日
- 遺産を受け取る方
- マンション
- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年11月27日
- 遺産を受け取る方
- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -
2025年11月19日
- 遺産を受け取る方
- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 生命保険金は相続財産? 受取人・他の相続人の平等な相続は実現可能?


















