- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約とは│契約前に押さえておきたい基礎知識と注意点
遺産相続コラム
財産管理委任契約とは│契約前に押さえておきたい基礎知識と注意点
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約

将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。
財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。
一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。
本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、財産管理委任契約(任意代理契約)の基礎知識
財産管理委任契約とは、財産を持つ人が自ら選定した代理人に財産管理を任せる契約です。「任意代理契約」と呼ばれることもあります。財産管理委任契約は、民事信託(家族信託)・法定後見制度・任意後見契約などと並んで活用されるケースが多い手続きです。各制度の特徴を理解したうえで、状況に合わせて使い分けましょう。
-
(1)財産管理委任契約・民事信託(家族信託)・法定後見制度の違い
財産管理委任契約・民事信託(家族信託)・法定後見制度は、いずれも将来の遺産相続のことを見据えて活用されます。それぞれの概要や違いは、下表のとおりです。
財産管理委任契約 民事信託(家族信託) 法定後見制度 概要 自分の財産管理を代理人(受任者)に任せる契約 自分の財産を受託者に信託譲渡し、契約の定めに従って管理してもらう契約 判断能力が不十分な方のために、後見人等が財産の管理や身上監護を行う制度 開始する方法 契約の締結 契約の締結 家庭裁判所の審判 対象者本人の判断能力の有無 判断能力に問題ない方が対象 判断能力に問題ない方が対象 判断能力が不十分な方が対象 財産の管理等を行う人の選任方法 委任者と受任者の合意のもと契約で定める 委託者、受託者及び受益者の合意のもと契約で定める 家庭裁判所が選任する 財産の管理方法に関するルール 委任者と受任者の合意のもと契約で定める 委託者、受託者及び受益者の合意のもと契約で定める 民法に従う(細かくは決まっていない) 管理する財産の所有者 本人(委任者) 受託者 本人 本人以外の受益者の設定 可 可 不可 身上監護の可否 不可 不可 可 信託法の適用 なし あり なし
財産管理委任契約は、契約によって代理人となる受任者に財産の管理を任せるものであり、その内容を契約で決定できる等多くの点で民事信託と類似しています。ただし、「管理する財産の所有者」については、財産管理委任契約は本人であるのに対し、民事信託は受託者(本人の代わりに財産管理をする人)という違いがあります。
また、民事信託とは異なり、財産管理委任契約は信託法が適用されません。
法定後見制度は、判断能力が不十分な人をサポートするための制度です。法定後見制度には家庭裁判所が関与するため、財産管理委任契約とは多くの点で異なっています。特に判断能力の低下が要件とされている点や、後見人等を家庭裁判所が選任する点などが、法定後見制度の大きな特徴です。 -
(2)財産管理委任契約は、任意後見契約と併用するケースも多い
財産管理委任契約は、任意後見契約と併用されるケースがよく見られます。
任意後見契約とは、将来的に判断能力が低下した際、任意後見人が財産の管理などを行う契約です。
財産管理委任契約を締結して以降、認知症の進行などによって判断能力が低下しているとみなされた場合、財産管理委任契約がその時点で終了することがあります。そのようなケースでも、任意後見契約を併用していれば任意後見契約に移行するため、継続して財産管理を行うことが可能です。
任意後見に移行した後は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が、任意後見人の事務を監督します。財産を持つ本人にとっては、自身の判断能力が失われたことに乗じて任意後見人が財産を横領するような事態を防げるので、安心です。
財産管理委任契約と任意後見契約はいずれも、財産管理を任せる人や、管理方法についてのルールなどを契約で自由に定めることができるため、互いに親和性があると言えるでしょう。 -
(3)財産管理委任契約が適しているケース
たとえば以下に挙げるケースでは、信頼できる受任者との財産管理委任契約を検討するのも選択肢の一つと言えるでしょう。
- 高齢または身体の不調が原因で、日常的な財産管理が難しくなった
- 長期間にわたって入院することになった
- 家族や親族以外の人に財産管理を任せたい
受任者による横領や使い込みのリスクがあるため、家族や親族以外の第三者を受任者として検討している場合には、特に慎重に考える必要があります。
受任者になれる人について法律上の定めはありませんが、法律に関する知見を豊富に持ち、高い職業倫理に基づいて業務を行う、弁護士などの専門職に依頼するのが安心です。
2、財産管理委任契約の3つのメリット
財産管理委任契約には、メリットとデメリットの両面があります。主なメリットは、以下のとおりです。
| メリット |
|---|
|
-
(1)メリット①|受任者や財産管理の方法を委任者の意思で自由に決められる
財産管理委任契約の受任者や、財産を管理する方法については、契約の定めによって自由に決めることができます。
信頼できる親族を受任者に選べば安心につながりますし、委任者本人がやることと受任者に任せることの区別や、財産の運用方法などを細かく指定できる点は大きなメリットと言えるでしょう。
たとえば、「銀行口座の管理だけを委任する」というようなことも可能です。 -
(2)メリット②|判断能力が衰えていなくても、財産管理を開始できる
財産管理委任契約は、判断能力が衰えていない段階でも締結が可能で、早い段階から財産の管理を開始することができます。これは、判断能力の著しい低下が要件とされている法定後見制度と異なる点です。
判断能力の下落をもたらさない病気や、身体的な問題などによって代理人に財産管理を任せたい場合にも、財産管理委任契約を活用することができます。判断能力が低下したとしても、任意後見への移行を前提に、その前段階として財産管理委任契約を活用することが可能です。 -
(3)メリット③|死後事務や任意後見契約も併せて依頼できる
財産管理委任契約では、特約で委任者が亡くなった後の死後事務についても定めることができます。身辺整理などの死後事務を信頼できる人に任せておけば、残された家族に迷惑がかかる心配が少なくなるので安心でしょう。
また、任意後見契約も併用できるため、万が一、認知症が進行してしまった場合などでも、継続的に財産の管理を任せることが可能です。
3、財産管理委任契約の3つのデメリット
財産管理委任契約は、弁護士のアドバイスを受けながら、先述のメリットを生かしつつ、以下のようなデメリットを緩和できる方法を検討しましょう。
| デメリット |
|---|
|
-
(1)デメリット①|金融機関などが対応してくれないことがある
財産管理委任契約は、社会的に十分普及しているとは言えません。
そのため、特に金融機関で預貯金関係の手続きを行う場合などには、財産管理委任契約をその根拠として示しても受け付けてもらえないことがある点に注意してください。 -
(2)デメリット②|本人の行為の取消権は認められない
財産管理委任契約を締結しても、委任者本人が自ら行った契約などを、受任者が取り消すことはできません。受任者が取消権を得るためには、家庭裁判所によって成年後見人等に選任される必要があります。
-
(3)デメリット③|受任者による横領や使い込みのリスクがある
財産管理委任契約の受任者は、委任者が所有する財産について、詳細な情報を把握できる立場となります。その立場を悪用して、受任者が委任者の財産を横領したり使い込んだりするようなトラブルが生じないとも限りません。
受任者による不正行為を防ぐためには、弁護士などの専門職を受任者に選任するのが安心につながる選択肢と言えるでしょう。専門職であれば横領などが行われる心配は低いといえます。
4、財産管理委任契約の受任者は誰に任せるか?
財産管理委任契約の受任者は、委任者が自由に選ぶことができます。
親族や弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が挙げられますが、適正な財産管理を確保し、トラブルを回避するには弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は法律の専門家であるとともに、高い職業倫理を保持しています。法的な知見を活かして適切な方法で財産管理を行ってもらえますし、横領などの不正行為の心配も小さくなります。
また、委任者本人の判断能力が落ちてしまった際、法定後見や任意後見への移行を弁護士にサポートしてもらうことが可能です。
遺産相続における弁護士の業務範囲は士業の中でも特に広いため、財産管理を含めた多くのニーズに柔軟に応えることができるでしょう。財産管理委任契約の締結を検討している方は、まずは弁護士にご相談ください。
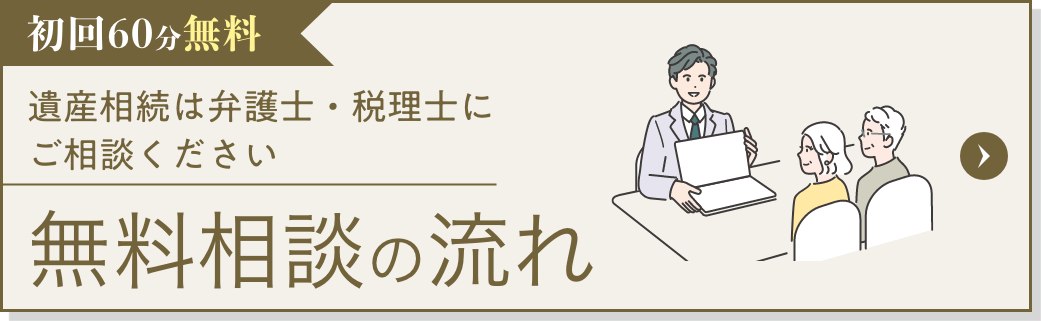
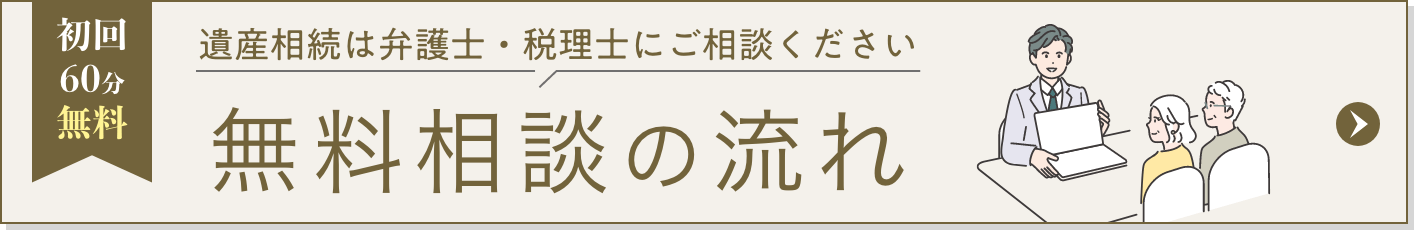
60分無料
5、まとめ
財産管理委任契約は、財産を持つ人が信頼できる人に財産の管理を任せる契約です。高齢や病気などによって自ら財産を管理するのが難しくなった場合や、将来的な判断能力の低下に備えたい場合などに活用しましょう。
しかし、横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性もあるため、財産管理委任契約の受任者には、法的知見と高い職業倫理を有する弁護士を選ぶのが安心です。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、弁護士が行政書士・司法書士・税理士等の隣接士業と必要に応じて連携し、財産管理から遺産相続まで幅広くサポートいたします。将来の遺産相続に備えたい方や、横領や使い込みなどのトラブルでお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を残す方)
-
2025年07月17日
- 遺産を残す方
- 死因贈与

贈与者が亡くなったことを条件とする贈与を「死因贈与」といいます。
死因贈与は遺言書による贈与(=遺贈)に似ていますが、実際は異なるものです。それぞれの特徴を踏まえたうえで、適切な方法を選択しましょう。
本記事では死因贈与について、遺贈との違いやメリット・デメリット、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年07月09日
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約

将来に備えて、財産管理委任契約を検討している方もいらっしゃることでしょう。
財産管理委任契約を締結すると、委任者(財産管理を委任する人)に代わり、受任者(財産管理を委任される人)が金融機関の預金を出し入れしたり、口座を管理したり、税金・年金の手続き等を行うことができるようになります。
一方、受任者による横領や使い込みといったトラブルが生じる可能性があるほか、認知症が進んでいる方は財産管理委任契約を締結することはできない可能性があるなどの制限があることにも注意が必要です。
本コラムでは、財産管理委任契約の基礎知識やメリット・デメリット、契約締結に向けての注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。 -
2022年11月28日
- 遺産を残す方
- 遺産相続
- 遺留分
- 生命保険
- 相続対策

遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。「特定の相続人に多くの財産を渡したい」「相続人同士揉めないようにしたい」とお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を残す方
- 財産管理委任契約とは│契約前に押さえておきたい基礎知識と注意点

















