- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 原戸籍とは? 取り方や戸籍謄本との違い、相続に必要な場面を解説
遺産相続コラム
原戸籍とは? 取り方や戸籍謄本との違い、相続に必要な場面を解説
- 遺産を受け取る方
- 原戸籍とは

遺産相続が始まると、手続きを進めるなかで、原戸籍(改製原戸籍謄本)の提出を求められる場合があります。
多くの方にとって原戸籍はなじみがない言葉であり、「原戸籍とは、どういう書類?」「相続手続きのどの場面で必要?」と、疑問を抱えている方も少なくないでしょう。
本コラムでは、原戸籍と戸籍謄本の違いや手続き方法、取得方法、また、原戸籍が必要な相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
1、原戸籍とは? 読み方・戸籍謄本との違い
「原戸籍」とは、新様式に作り替えられる前の戸籍簿(=家族関係に関する情報が記載された書類)のことです。相続手続きでは、原戸籍の写しである「改製原戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
-
(1)原戸籍とは
「原戸籍」は、正式名称を「改製原戸籍」といいます。
「げんこせき」と読むのが正しいのですが、「現在の戸籍(=現戸籍)」と区別するために「はらこせき」と呼ばれることもあります。
明治5年(1872年)に戸籍法が施行されて以来、現在に至るまで5回の戸籍簿の様式変更(=戸籍改製)が行われました。様式変更の際には、戸籍簿が新様式に作り替えられますが、その際に作り替えられる前の戸籍簿が「改製原戸籍」です。
直近では、平成に入ってから戸籍のコンピューター化が行われました。
コンピューター化以前の紙の戸籍簿は「平成改製原戸籍」と呼ばれており、現在において「改製原戸籍」と言う場合は、この平成改製原戸籍を指すのが一般的です。
これに対して、それ以前の改製原戸籍は「昭和改製原戸籍」などと呼ばれることがあります。 -
(2)改製原戸籍謄本と戸籍謄本の違い
改製原戸籍の写しは「改製原戸籍謄本」と呼ばれ、本籍地の役所で取得することが可能です。
これに対して、コンピューター式戸籍簿の写しは「戸籍全部事項証明書」であり、「戸籍謄本」と通称されています。
戸籍謄本も本籍地の役所で取得できますが、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いてコンビニでも取得できる場合があります。 -
(3)改製原戸籍の保存期間
現行の戸籍法では、改製原戸籍が保存される期間は、改製年度翌年から150年とされています。
しかし、平成22年(2010年)の戸籍法改正以前の保存期間は、改製の種類によって50年・80年・100年のいずれかとされていました。
そのため、改製から現時点までの期間が150年以下であっても、改製の時期によっては改製原戸籍が破棄されている可能性があります。
改製原戸籍が残っているかどうかは、市区町村役場に確認しましょう。
2、相続手続きの流れ・改製原戸籍謄本が必要となる場合
家族が亡くなった際には、相続手続きを行わなければなりません。その際、家族の状況や手続きの種類によっては、戸籍謄本・除籍謄本に加えて改製原戸籍謄本の提出が求められることがあります。
-
(1)相続手続きの大まかな流れ
相続手続きは、大まかに以下の流れで進めます。
① 遺言書の有無を確認する
被相続人の遺品を探すほか、公証役場や法務局での検索・照会を通じて、遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、原則としてその内容のとおりに遺産を分けます。
② 相続人の調査
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。
③ 相続財産の調査
被相続人が死亡時に所有していた財産を調査し、遺産分割の対象を確定します。
④ 相続放棄・限定承認の申述
相続財産の調査の結果、被相続人に借金があることが判明した場合などには、相続放棄(民法第939条)または限定承認(民法第922条)を行うことも検討すべきです。
相続放棄および限定承認は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申述書などの必要書類を提出して行います。期限は原則として、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内です。
⑤ 遺産分割協議・調停・審判
相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決めます。合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停では、調停委員が仲介者として各相続人の言い分を聞き、遺産分割に関する合意形成を目指します。
遺産分割調停も不調に終わった場合は、家庭裁判所が審判を行い、遺産分割の方法について結論を示します。
⑥ 相続税の申告と納付
遺産分割の結果に従い、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に対して相続税の申告を行い、相続税を納付します。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
⑦ 相続財産の名義変更
遺産分割において決まった内容に従い、相続財産の名義変更を行います。 -
(2)改製原戸籍謄本が必要となる状況・手続きの例
相続において改製原戸籍謄本の提出を求められるのは、被相続人が生まれてから、亡くなるまでの戸籍の変遷を証明する必要がある場合です。
具体的には、被相続人が戸籍のコンピューター化以前に出生した場合は、改製原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。戸籍のコンピューター化の時期は自治体により異なりますので、詳しくは各自治体のホームページなどでご確認ください。
改製原戸籍謄本が必要となる主な相続手続きは、以下のとおりです。- ① 相続人の確定
- ② 相続放棄・限定承認の申述
- ③ 以下の相続財産の名義変更(相続手続き)
・ 預貯金
・ 有価証券
・ 不動産
なお、改製原戸籍がすでに廃棄されている場合は、本籍地の市区町村役場に申請すれば廃棄済証明書を発行してもらうことが可能です。廃棄済証明書を提出すれば、本来必要である原戸籍がなくても、相続手続きを進めることができます。
3、改製原戸籍謄本の取得方法
相続手続きにおいて改製原戸籍謄本が必要となった場合には、市区町村役場に対して取得申請を行う必要があります。
改製原戸籍謄本の取得を申請できる人・申請先・申請方法を解説します。
-
(1)改製原戸籍謄本の取得を申請できる人
改製原戸籍謄本の取得を申請できるのは、原則として以下のいずれかに該当する人に限られます。
① 本人等- 改正原戸籍に記載されている本人
- 本人の配偶者
- 本人の直系親族(父母、祖父母、子ども、孫など)
② 第三者- 自己の権利行使または義務履行など、改製原戸籍謄本を取得することについて正当な理由がある人
③ ①または②の代理人- 法定代理人(親権者、成年後見人など)
- 任意代理人(弁護士、司法書士、税理士など)
ただし弁護士などは、上記のいずれにも該当しない場合でも、業務上必要である場合に限り、職務上請求によって改製原戸籍謄本を取得することが可能です。
-
(2)改製原戸籍謄本の取得の申請先・申請方法
改製原戸籍謄本の申請先は、改製原戸籍が保管されている市区町村役場です。
改製原戸籍は、改製がなされた時点での本籍地の市区町村役場に保管されています。窓口で申請すれば、改製原戸籍謄本の交付を受けることが可能です。手数料は1通当たり750円となっています。
また、改製原戸籍謄本は郵送でも取り寄せることが可能です。郵送による申請先は、市区町村役場のウェブサイトなどで確認しましょう。
郵送による申請を行う場合、改製原戸籍謄本が届くまでには1週間から2週間程度を要するため、余裕をもって申請することをおすすめします。
なお、戸籍謄本とは異なり、改製原戸籍謄本をコンビニで取得することはできません。

4、弁護士がサポートできる相続手続きの例
相続手続きを進めるに当たっては、改製原戸籍謄本などの見慣れない書類が必要になることもあります。手続きの内容も複雑かつ多岐にわたるため、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
弁護士は幅広い相続手続きについて、各手続きが滞りなく進むようにご依頼者さまをサポートすることが可能です。
以下に挙げるのは、ベリーベスト法律事務所ができる相続サポートの一例です。
公証役場・法務局における検索・照会や、検認手続きなどをサポートいたします。
② 相続人・相続財産の調査
職務上請求を活用してスムーズに書類を取り寄せ、漏れがないように相続人・相続財産の調査を行います。
③ 相続放棄・限定承認の申述
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを取り寄せた上で、期限に間に合うように申述手続きを代行いたします。
④ 遺産分割協議・調停・審判
依頼者の代理人として対応し、有利な内容で遺産分割が行われるようにサポートいたします。
⑤ 相続税の申告・納付
グループに所属する税理士と連携して、申告書の作成をサポートいたします。
⑥ 相続財産の名義変更
預貯金や有価証券などの相続手続きをサポートするほか、不動産の相続登記についても、グループに所属する司法書士と連携してサポート可能です。
ベリーベスト法律事務所は、相続に関するあらゆる手続きにご対応いたします。相続手続きについてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
60分無料
5、まとめ
相続手続きでは、原戸籍(改製原戸籍謄本)の提出を求められることがあります。
書類を用意する際は、市区町村役場に対して取得申請を行い、入手するようにしましょう。なお、改製原戸籍謄本をコンビニで取得することはできないため、余裕をもって申請するようにしてください。
原戸籍を含めて、どのような書類が必要なのか分からない方や、相続手続きを自力で進めるのが不安な方は、経験豊富な弁護士に依頼するのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。
相続手続きの円滑な進行や、遺産分割トラブルの解決などを弁護士がサポートいたしますので、相続手続きの進め方についてお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
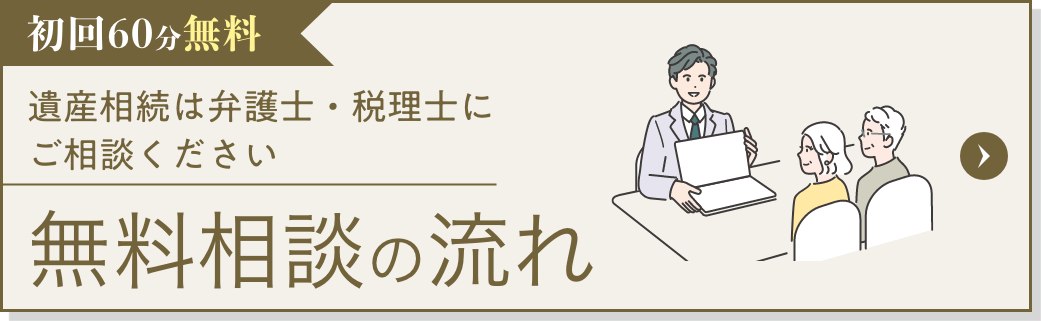
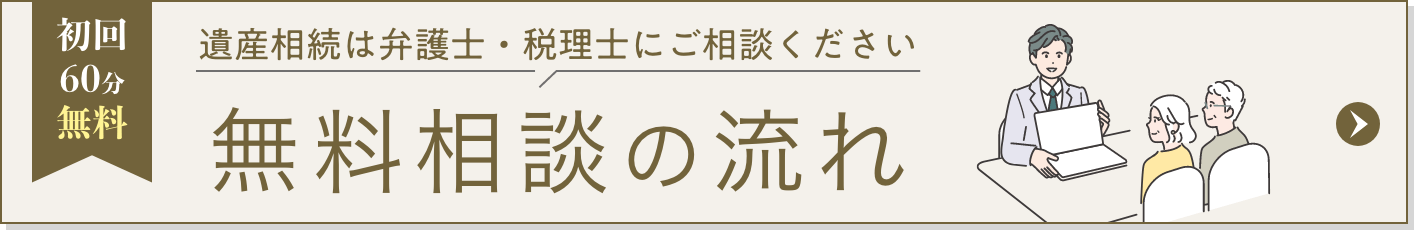
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺産を受け取る方)
-
2025年12月11日
- 遺産を受け取る方
- マンション
- 相続

マンションを相続する際には、多くのステップを踏んで手続きを行う必要があります。相続税の納税義務が生じる可能性も高いでしょう。
適切に対応するためにも、弁護士や税理士のサポートを受けながら手続きを進めることをおすすめします。
本記事では、マンションの相続における期限や相続税の目安、遺産分割する際の手段などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年11月27日
- 遺産を受け取る方
- 被相続人とは

被相続人とは、法律上「亡くなった人」を指す言葉です。そして、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。
相続手続きでは、この「被相続人」と「相続人」の関係性や相続順位によって、誰がどのくらいの財産を受け取れるのかが決まります。遺産分割の際に、相続人同士でもめることも少なくありませんので、相続に関する基礎知識を身につけておくことが大切です。
今回は、被相続人や相続順位など、相続に関する基礎知識から、遺産相続を弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。 -
2025年11月19日
- 遺産を受け取る方
- 離婚した親の相続

顔も知らない親族や弁護士から、思いがけず相続手続きへの協力を求められ、戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。長年連絡を取っていなかった親の相続であれば、なおさら驚きや不安を感じるのも当然です。
子どもである以上、たとえ親が離婚していたとしても、法律上は被相続人(亡くなった方)の相続人となるのが原則であるため、基本的に相続手続きの対象になります。ただし、亡くなった親の遺産がプラスの財産ばかりとは限らず、借金などのマイナスの財産を背負ってしまうリスクもあるため、相続するかどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
今回は、離婚した親でも子どもに相続権があるのか、相続分はどのくらいかといった基礎知識から、相続したくない場合の「相続放棄」の方法や期限などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺産を受け取る方
- 原戸籍とは? 取り方や戸籍謄本との違い、相続に必要な場面を解説


















