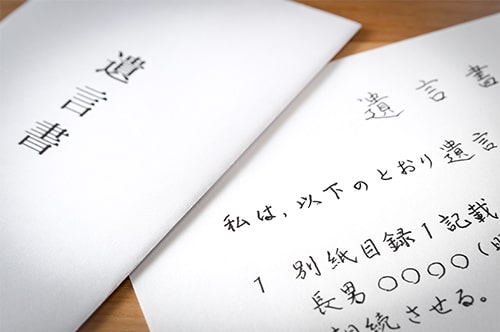- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 公正証書遺言でも遺留分は請求される? 侵害額請求の注意点を解説
遺産相続コラム
公正証書遺言でも遺留分は請求される? 侵害額請求の注意点を解説
- 遺留分侵害額請求
- 公正証書遺言
- 遺留分

遺言書によって指定された相続分があまりにも偏っていた場合には、相続人同士で「遺留分侵害額請求権」が争われる可能性があります。
遺産相続においては、たとえ公正証書遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていたとしても、他の相続人に認められている「遺留分」を侵害する部分について遺留分侵害額請求として金銭請求されることになります。
もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切にトラブルを解決するため、弁護士に相談することをおすすめします。本コラムでは、遺留分と公正証書遺言の関係や、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続き・対応・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、遺留分とは?
「遺留分」とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合のことです。
遺留分を下回る遺産しか相続できなかった相続人は、遺産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行って、侵害された分の金銭の支払いを受けることができます。
-
(1)遺留分が認められる人・認められない人
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法第1042条第1項)。
具体的には、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子ども、子どもがいない場合には直系尊属(被相続人の両親・両親が死亡している場合には祖父母)にも遺留分が認められます。
また、被相続人の子どもが死亡しており、孫が代襲相続人となる場合には、孫にも遺留分が認められます。
ひ孫以降も同様です。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹については、相続人であっても遺留分は認められません。
被相続人の甥や姪が代襲相続人となる場合も、同じく、遺留分は認められません。 -
(2)遺留分の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となるのは、以下の財産の総額から、相続債務の全額を控除した金額です(民法第1043条、第1044条)。
① 相続財産
被相続人が死亡時に有した財産。(遺贈や死因贈与をされた財産も含める)
② 以下の期間中に行われた生前贈与
(a)相続人に対する贈与の場合
相続開始前10年以内に行われたものに限る(ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、それよりも前にしたものについても含める)
また、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限る。
(b)相続人以外の者に対する贈与の場合
相続開始前1年間以内に行われたものに限る(ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、それよりも前にしたものについても含める) -
(3)遺留分割合の決まり方
遺留分は、以下の割合です。これを実際の相続人で法定相続分に応じて割り付けられます(民法第1042条第1項)。
- ① 直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
- ② それ以外の場合:2分の1
(例)
-
相続人が配偶者A、子どもB、子どもCの3名の場合の遺留分割合
配偶者A:4分の1
子どもB:8分の1
子どもC:8分の1
-
相続人が父D、母Eの場合の遺留分割合
父D:6分の1
母E:6分の1
-
相続人が配偶者のみの場合
配偶者:2分の1
60分無料
2、公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求は可能
相続人には、遺言書の内容に関わらず、遺留分を受け取る権利があります。
自筆証書遺言に限らず、公正証書遺言がある場合にも、事情は変わりません。
公正証書遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く取得した者に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるのです。
-
(1)公正証書遺言によって遺留分が侵害される場合の例
公正証書遺言によって遺留分が侵害されるケースとしては、以下のような事例があります。
- 公正証書遺言において、長男だけにすべての遺産を相続させる旨が記載されていた場合
- 公正証書遺言において、被相続人と仲が悪かった子どもの相続分がゼロと指定されていた場合
- 配偶者や子どもがいるにもかかわらず、公正証書遺言において、遺産の大半を愛人に相続させる旨が記載されていた場合
-
(2)遺留分侵害額の計算方法・計算例
遺留分侵害額は、以下の計算式によって求めます。
遺留分侵害額=遺留分額-相続により取得した金額
(遺留分額=遺留分の基礎財産総額×遺留分割合)
<設例>- 相続人は配偶者A、子どもB、子どもCの3名
- 相続財産が3000万円
- 子どもBに対する生前贈与が1000万円(相続発生の8年前)
- 公正証書遺言によって指定された相続分は、Aが2100万円、Bが700万円、Cが200万円
Cの遺留分額
=(3000万円+1000万円)×8分の1
=500万円
Cの遺留分侵害額
=500万円-200万円
=300万円
→CはAに対して225万円、Bに対して75万円の遺留分侵害額を請求することができる。
※設例において、Cの遺留分を侵害する遺贈・贈与は、「Bに対する1000万円の生前贈与」、「Aに対する2100万円の遺贈」、「Bに対する700万円の遺贈」の3つです。
受遺者(遺贈を受ける人)と受贈者(贈与を受ける人)があるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します(民法第1047条第1項第1号)。
そのため、上記3つのうち、「Aに対する2100万円の遺贈」「Bに対する700万円の遺贈」の2つのみが遺留分侵害額請求の対象となります。
受遺者が複数あるときは、目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担しますので(同項第2号)、遺贈の価額の割合(2100万円:700万円=3:1)に応じて、Aは225万円、Bは75万円の遺留分侵害額を負担する。
3、遺留分侵害額請求を受けた場合の手続きの流れ
もし遺留分侵害額請求を受けた場合には、解決までに以下のような手続きを経る必要があります。
-
(1)内容証明郵便による遺留分侵害額請求
最初は、内容証明郵便などによって遺留分侵害額請求を受けるケースが一般的です。
記載されている遺留分額と計算根拠を確認して、請求内容が妥当であるかどうかをきちんと検討しましょう。財産に不動産や非上場株式が含まれる場合には、その評価方法も含めて検討する必要があります。 -
(2)請求者との協議
トラブルを大きくせずに早期の解決を目指す場合には、請求者(遺留分権利者)との協議に応じて、話し合いを進めていくのがよいでしょう。
遺留分侵害額に関する法的根拠を確認したうえで、資金調達のめどなどに関して相手と話し合い、合理的な落としどころを探りましょう。
遺留分の精算方法に関して合意した場合には、その内容を合意書にまとめましょう。 -
(3)遺留分侵害額請求調停
遺留分に関して協議がまとまらない場合には、侵害された側が、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が双方の主張を公平に聞き取ったうえで調整を図ります。
最終的に、裁判官が提示する調停案に双方が合意すれば、調停は成立です。
成立した調停の内容は調停調書に記載されて、その内容に従って遺留分の精算が行われることになります。 -
(4)遺留分侵害額請求訴訟
遺留分を侵害された側が、地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に対して訴訟を提起することもできます。訴訟に先立って調停をする義務はありませんので、最初から訴訟を提起することも可能です。
訴訟では、原告(訴訟を提起した側)が遺留分侵害額請求権の存在を立証して、被告がそれに対して反論(反証)を行います。
裁判所は、当事者双方の主張を検討したうえで、遺留分侵害額請求権の有無や金額について判決を言い渡します。
判決に至る前に、裁判所の主導の下で、和解の話し合いをすすめることもあります。
和解が成立せず、判決になった場合には、その判決が確定した後に、判決の内容に従って遺留分侵害額として認められた金額の支払いが行われます。
4、遺留分侵害額請求を受けた場合に注意すべきポイント
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合には、トラブルのない適切な解決を目指すため、以下のような点に注意する必要があります。
ご自身で対応することに不安があれば、弁護士に依頼することを検討してください。
-
(1)内容証明郵便を受け取ったら、無視せずに対応すべき
遺留分侵害額請求の内容証明郵便を受け取ったら、無視して放置することは避け、速やかに対応を開始してください。
内容証明郵便を無視していると、調停や訴訟に発展してしまう可能性が高いためです。
遺留分に関する問題を早期に解決するためには、早い段階から協議を行うことが必要です。内容証明郵便を受け取ったら無視せず、すぐに弁護士にご相談ください。 -
(2)遺留分侵害額請求権の時効期間は1年|時効が完成していないかを要確認
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年で時効消滅します。
消滅時効が完成した後は、時効を援用することにより、遺留分侵害額の支払債務を免れることができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合は、相手方の請求権が時効消滅していないかどうかも確認することをおすすめします。 -
(3)請求者が過去に生前贈与を受けていないかどうかを確認する
遺留分侵害額請求をしてきた相手方が、被相続人から過去に生前贈与を受けていると、遺留分侵害額が減少する可能性があります。
その金額によっては、遺留分侵害額を一切支払わずに済む可能性もあるのです。
相続人に対する生前贈与の場合には、相続開始前10年以内に行われたものであり、それが婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本とするためであれば、遺留分の基礎財産に含まれます。
相手方がこの期間に生前贈与を受けていた場合には、遺留分侵害額請求に関する有力な反論材料となりますので、調査をすることも大切です。
60分無料
5、まとめ
遺留分侵害額請求を受けた場合は、相手方の請求に根拠があるかどうか、法的な観点から十分に検討したうえで対応することが重要です。
遺留分に関してトラブルが生じた場合には、ご自身の利益を守るためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、遺留分問題を含めて、遺産相続に関する法律相談を承っております。弁護士が丁寧にヒアリングを行ったうえで、相続トラブルを1日でも早く解決するためにサポートいたします。
また、相続税申告や相続登記についても、ベリーベストグループに在籍している税理士にご相談いただくことが可能です。
遺留分やその他の問題など、遺産相続でトラブルが起こった場合には、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
- 所在地
- 〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]
03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
同じカテゴリのコラム(遺留分侵害額請求)
-
2026年01月07日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分
- 計算

生前贈与や遺言書によってほかの相続人が優遇された結果、自分の相続分が少なくなってしまい、対処をお考えの方もいるでしょう。その場合、財産を多く取得した相続人に対し、遺留分を請求できる可能性があります。
遺留分を請求するには、請求できる金額を事前に計算しておくべきです。しかし、遺留分額の計算を正確に行うには手間がかかるため、弁護士への相談も検討しましょう。
本記事では、遺留分額の計算方法や、遺留分が侵害された場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年10月15日
- 遺留分侵害額請求
- 遺言書
- 全財産
- 無効
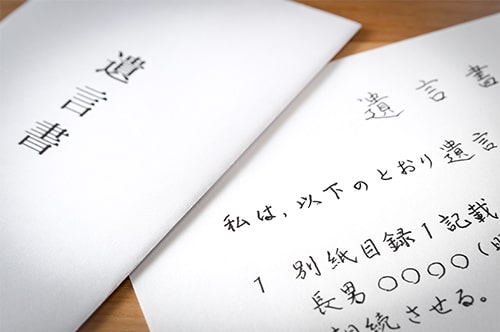
「全財産を長男に相続させる」「他の相続人には何も相続させない」といった遺言書が見つかった場合、不公平だと感じませんか?
遺言書には「遺言自由の原則」があるため、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則として有効です。ただし、すべての場合にそれが通用するとは限りません。遺言書の有効性が疑われる場合には遺言を無効とできる可能性があります。また、法定相続人の最低限の取り分である「遺留分 (いりゅうぶん)」が侵害されている場合には、相続した相続人等から一部を取り戻せる可能性があります。
本コラムでは、「全財産を一人に相続させる」と書かれた遺言書が無効とされる可能性があるケースや、有効な遺言でも相続財産を確保する方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2025年07月23日
- 遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求
- 調停

生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
- 弁護士による相続相談
- 遺産相続コラム
- 遺留分侵害額請求
- 公正証書遺言でも遺留分は請求される? 侵害額請求の注意点を解説